|
わたしの寄席: 平成30年八月中席浅草演芸ホール
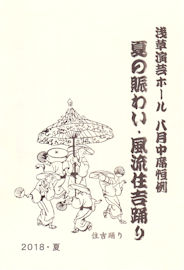 浅草演芸ホールの八月中席昼の部は毎年恒例の「住吉踊り興行」です。 今年40年目となる「住吉踊り」の人気は今も続いていて、開演30分前の午前10時には入口で整理券をもらって並ぶ人の長い列が出来ています。 初代の座長は先代雷門助六師、二代目は古今亭志ん朝師、そして間に三遊亭金馬師をはさんで、平成21年から座長を引き継いだ金原亭駒三師を主任とする興行も早いもので今年で10年となります。 今年も毎回常連の仲間4名がそれぞれにお弁当と飲み物を持参して、賑やかに寄席見物をしました。 データ: 平成30年8月16日 浅草演芸ホール 昼の部
入り 開演時 七分 中入 九分 終演時 満員 終演 16:30 コメント: 10時半に前座が上がって、大喜利の住吉踊り終演まで、6時間の長丁場です。いつものように体力の温存を図って、のんびりと見物することにしました。昨年も見かけたおしどりは男女のコンビで器用な針金細工で客席を沸かせました。ベテラン漫才の笑組は今年で32年。最初は内海好江さんのお弟子で高座に上がり、好江さんが亡くなってからは志ん朝師の一門となったことなど思い出されます。志ん朝師の後、3年ほど住吉踊りの座長を務めた金馬師の息子、金時の「真田小僧」で最初の中入りになりました。 講談の神田茜は自作と思われる得意の「幸せの黄色い旗」。楽一の紙切りは客席からのリクエストで「住吉踊り」、「阿波踊り」と踊りが続きました。ベテラン女流講談の紅師には存在感があります。子猫の軽妙な動物物まねがあり、住吉踊りの番頭役を務める吉窓がひょうひょうとした「半分垢」の後、円丈で二度目の中入りです。 翁家社中はベテランの小楽が休演で和助、小花の若手コンビが切れの良い曲芸を見せてくれました。雷蔵の「新聞記事」は手堅いネタです。ロケット団の漫才は近頃脂がのって来たようです。歌之介の爆笑漫談で本来のお中入りになりました。 中入り後に上がった橘家橘之助は昨年11月に三遊亭小円歌から二代目を襲名。初代にならって「浮世節」を看板に掲げています。初代が得意にしていた「たぬき」で膝替り、駒三の「権助芝居」の後、大喜利の住吉踊りが楽屋総出で約50分掛けて演じられ、最後に会場一杯の手締めで無事に打ち上げとなりました。 あとがき:  「住吉踊り」は今年で40年目になりました。中入りや終演後には出演者が記念の手ぬぐいを売り歩く姿がみられ、こちらもご祝儀代わりに一本買いました。 「住吉踊り」は今年で40年目になりました。中入りや終演後には出演者が記念の手ぬぐいを売り歩く姿がみられ、こちらもご祝儀代わりに一本買いました。改めて筆者の「住吉踊り」見物を振り返ってみると、1997年から毎年通っていることが分かりました。それ以前にも時々見た記憶があるのですが、とりあえず22年の皆勤となりました。 … だからどうなんだと言われても、特に自慢することはありません。 終演後は主な出演者が演芸ホールの前に出て、手ぬぐいを売りながら愛嬌を振りまいていました。お気に入りの芸人さんと一緒に写真を撮ったりする図々しい客もいます。実は私もその一人でした。 演芸ホールを出たあとは、今年も仲間といつもの居酒屋さんで寛ぎました。 平成30年8月19日 稲林記
|