|
わたしの寄席: 平成29年八月中席浅草演芸ホール
 毎年の恒例、浅草演芸ホールの昼席「住吉踊り興行」です。 毎年の恒例、浅草演芸ホールの昼席「住吉踊り興行」です。住吉踊りとのお付き合いもかなり長くなりました。2001年(平成13年)の住吉踊りが終って間もなく、それまで座長を勤めていた古今亭志ん朝師が亡くなられた時がひとつの転機でしたが、その後、金馬師が平成20年まで座長を勤め、平成21年から座長を引き継いだ駒三師になってから早くも9年が過ぎています。 今年は毎回常連の仲間に加えて、自発的?に参加を申し出た3人と合せて6名の賑やかな寄席見物になりました。 データ: 平成29年8月18日 浅草演芸ホール 昼の部
入り 開演時 七分 中入 満員 終演時 立見 終演 16:40 コメント: 開演時刻ちょうどに高座に上がった前座はあお馬、後で調べると柳家小せんのお弟子です。女流の二つ目が二人続けて登場、風子は春雨や雷蔵、ちよりんは古今亭菊千代が師匠です。若手の芸人さんの素性調べはこの辺にして、漫才で登場のおしどりは針金細工で場内を最初に沸かせました。スマートな芸です。ときんの名で上がったのは金時の弟子で今年の春に時松から真打になったようです。若い芸人さんの顔と名前が一致するようになるのは時間がかかります。志ん陽の「たらちね」あたりから落着いた高座になり、金八の「四人ぐせ」で最初の中入りです。 紙切りの林家楽一は若手で切れの良い手際を見せてくれました。難題と思われる「阿修羅(興福寺)」を見事に切り分けました。ベテラン左橋の「替り目」、講談の茜は得意のバスガイドもので「幸せの黄色い旗」を演じました。 ふるさとコンビというのは初めてだったのですが、ギターを持った結城たかしの脇に和服で三味線を持って出て来たのが遊平・かほりの夫婦漫才でお馴染みだった大空遊平なので驚きました。演歌を聴かせる楽しいコンビの登場を喜びながら、かほりさんはどうしたのか?と思いました。あとで調べてみると、遊平・かほりのコンビは二年前に解散、結婚も解消したとのことです。 そういうことには関係なく、高座の方はとん馬、歌る多と進んでゆきます。ものまねの江戸家小猫ときいて、想像したのは先代でした。いまの小猫は先代の小猫の息子です。家の芸とも言える物真似芸の健在を見せてくれました。吉窓の「「たぬき」、長老円丈の漫談で二度目の中入りになります。 この後、和服で日本手品(和妻)を披露した花島皆子、雷蔵、馬風、にゃん金の漫才に続いて、文楽の「悋気の火の玉」はおつな噺です。人気者歌之介で本来のお仲入となりました。 志ん弥の「浮世床」は将棋の場面のみ、三味線漫談の小円歌は今年の秋に立花家橘之助を襲名するそうで、得意の「両国風景」を熱演しました。駒三の「後生鰻」で番組を終えた後、大喜利の住吉踊りが楽屋総出で約50分掛けて演じられ、最後に会場一杯の手締めで開演から6時間余りの長い昼席が無事に打ち上げとなりました。 あとがき: 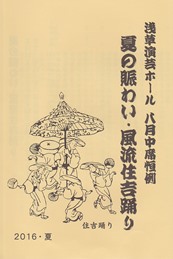 「住吉踊り」は今年で39年目になるそうです。 「住吉踊り」は今年で39年目になるそうです。長く見つづけている中で、今年は芸人さんの顔ぶれの変化を特に印象強く思いました。個々にはそれぞれ文中で触れた通りですが、改めて確認してみると、物故者も少なくありません。お盆という季節がそのようなことをしみじみと感じさせてくれるのかも知れません。 次々に高座に登場する芸人さんの姿を眺めていると時間がゆるやかに流れて行きます。寄席演芸の世界にもいろいろな移り変わりがあるようですが、芸の継承が穏やかに進んでいるのは嬉しいことです。 演芸ホールを出たあとで、仲間と向かうのはいつもの居酒屋さんです。下町らしい、気さくなお店でさっきまで見ていた演芸の感想を語り合いました。 平成29年8月19日 稲林記
|