|
わたしの寄席: 平成28年八月中席浅草演芸ホール
 今年もお盆興行の季節となりました。 毎年の恒例、浅草演芸ホールの昼席「住吉踊り興行」に仲間と誘い合わせて出かけました。 今月は3日に上野鈴本演芸場の昼席に行き、6日の土曜日には神保町の居酒屋さんで開催された「酔の助寄席」という催しにも顔を出しましたので、だいぶ寄席づいてきました。 浅草は何時出かけてもにぎやかです。10時前に入場すると客席は既に大勢のお客さんで埋まっていました。 データ: 平成28年8月16日 浅草演芸ホール 昼の部
入り 開演時 七分 中入 満員 終演時 立見 終演 16:35 コメント: 前座のあんこは林家しん平のお弟子だそうで女性です。春風亭昇也は昇太のお弟子と、例によって師匠調べが続きます。この日は客席に小学生と思われる女の子が何人かいました。紙切りの注文の一つはその中から出た「太鼓を叩いている男の人」という可愛いお題でした。 ユニークなロケット弾の漫才の後、白酒の「宗論」には独自の改作が施されていました。続く金八の「弥次郎(うそつき弥次郎)」で最初の中入りとなります。」 落ちついた小樂・和助コンビの太神楽曲芸の後、懐かしい六代目圓生の出囃子「正札附き」で登場した圓王は「本膳」。中頃に一人で登場した昭和こいるは相棒の昭和のいるのケガ、このところ組んでいるあした順子の体調不良と、事情を説明して漫談で笑いを取りました。2回目の中入り前、いまや中堅の古今亭志ん輔は色気のある「宮戸川」を前段のところまで。 珍しく浴衣姿で登場した花島皆子のマジックは「和妻」と呼ばれた日本手品の中から「袖たまご」と「半紙」の手品を品よく見せてくれました。雷蔵は得意の「八の字問答」、馬風、にゃん・金の漫才に続いて爆笑王と言ってもよい歌之介はこの日も漫談で客席を沸かせました。 中入り後の楽しみ、小円歌・小菊の三味線競演は全曲目を記します。 ①夏はうれしや、②お江戸日本橋、③おてもやん、④縁かいな、⑤都々逸、⑥どんどん節、⑦長唄「京鹿子娘道成寺」の合方。 最後の「道成寺」合方は三味線の連れ弾きで息のあったところを見せてくれました。昨年から始めたこの形は、その昔の「人形・お鯉」という女芸人コンビの音曲を思い出せてくれます。 主任で「住吉踊り」座長の駒三は軽妙な「権助芝居」で締めました。 お目当ての「住吉踊り」は今年もいろいろな趣向を楽しむことが出来ました。いつものように「伊勢音頭」で始まり、「吃又」、「深川」から「後越後獅子」に進み、サラシの合方の中では開催中のオリンピックに因んだ水泳のシーンが挿入されました。最後は「かっぽれ」でにぎやかに目出度くお開きとなります。 あとがき: 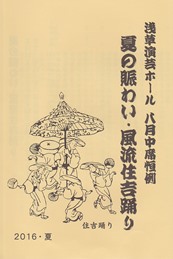 「住吉踊り」の冒頭、ご挨拶の中で住吉踊り興行が今年で38年目になることが語られました。私のレポートでも2000年(平成12年)が22年目であることが記されています。同じレポートで4年連続で見に来ていることを語っていますので、1997年(平成9年)の19年目から20年連続で「住吉踊り」を見てきたことになります。 「住吉踊り」の冒頭、ご挨拶の中で住吉踊り興行が今年で38年目になることが語られました。私のレポートでも2000年(平成12年)が22年目であることが記されています。同じレポートで4年連続で見に来ていることを語っていますので、1997年(平成9年)の19年目から20年連続で「住吉踊り」を見てきたことになります。だからどうなんだということもありませんが、20年の間に志ん朝師匠をはじめとして亡くなった芸人さんも少なくありません。一方で、若い芸人さんの登場、成長の姿も楽しむことができています。 年中行事のようにお盆の浅草に足を運ぶことも、いろいろな思いを蓄積させてくれました。「芸能の感動」というと言葉が軽いようですが、日本の芸のベースを共有する寄席演芸の中からその場に居合わせることの仕合せを味わっています。 平成28年8月17日 稲林記
|