|
わたしの寄席: 平成27年八月中席浅草演芸ホール
え~、お盆吉例の住吉踊り興行、毎年一緒に見物している古い仲間の誘いを受けて出かけました。乗換駅の上野でお昼の軽食と冷たい飲み物を買って行くのもいつもと同じです。上野か  ら地下鉄に乗換えて田原町から国際通り、雷門通りの交差点で信号を渡って1本北側の路地(食通街)を抜けて、すし屋通りを左折すると間もなく浅草演芸場の看板が見えてきます。 ら地下鉄に乗換えて田原町から国際通り、雷門通りの交差点で信号を渡って1本北側の路地(食通街)を抜けて、すし屋通りを左折すると間もなく浅草演芸場の看板が見えてきます。この興行に限って10時に開場、10時30分開演というのは通常の昼席よりも1時間半くらい早いのですが、出足はよく、開演時刻に入場すると客席は半分以上埋まっていました。 落語協会だけでなく芸術協会からも常連の出演者が参加する住吉踊り興行は出演者が多く、大喜利を含めると6時間に及ぶ番組をしっかり味わうためには体力と気力の充実を必要とします。 データ: 平成27年8月18日 浅草演芸ホール 昼の部
入り 開演時 八分 中入 満員 終演時 満員 終演 16:30 コメント: 最初に登場した前座の名前は’あおもり’という…。めくりに書いてない亭号は想像がつきません。今年初めて参加した昇也は春風亭昇太の弟子ということはすぐに分ります。続く女流のちよりんは古今亭菊千代の弟子、と師匠の詮索ばかりしていても能がありません。ビート漫才のロケット団の後、師匠志ん朝の前名、朝太から真打になった古今亭志ん陽の「代書屋」で最初に客席がはじけました。一皮むけた気持の良い芸を見せています。翁家社中の太神楽曲芸は今年も和楽の姿がなく、若い和助がきびきびと口上を勤め、力強い芸を見せてくれました。圓王のところで最初の中入りがありました。ちょうどお昼の時間となり食事に気を取られていたのでネタを書き漏らしましたが、この人らしい好感のもてる高座でした。にゃん・金の突撃漫才の後、小文治は珍しい噺でした。ネタの名前は最後に言ったひと言から記録しました。笑組の軽妙な漫才の後、菊千代に続く菊之丞は「死ぬなら今」という変わった名前の噺ですが、菊之丞からみれば大師匠にあたる十代目の馬生がときどき寄席で演じたのを憶えています。いつも美しい花島皆子さんの奇術と住吉踊り常連の菊春が「替り目」で笑わせた後、市馬は「雑排」をさらっと演じました。このあたりの感覚が寄席の味わいです。 二度目の中入りの後、それぞれ相方が入院中という、こいる・順子の熟年漫才、そして平成の爆笑王になりつつある歌之介の漫談、雷蔵の後はまねき猫の動物物真似でなごみ、御大馬風の漫談で本来の中入り(お仲入り)になります。 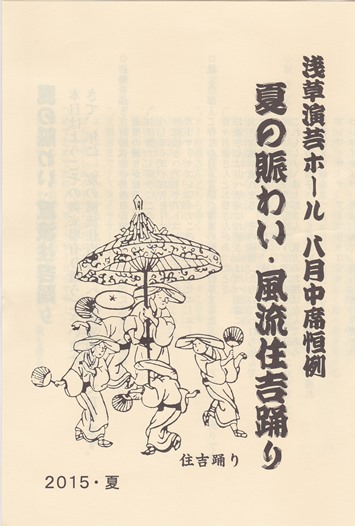 志ん弥の「湯屋番」に続いて、いつもは一人で高座を勤める小円歌と小菊がコンビで音曲を聴かせます。軽妙な話を挟みながら「夏はうれしや」、「相撲甚句」を唄い、小円歌が「佃の合方」、小菊が「新内流し」を弾くと、楽屋でまねき猫が蛙とこおろぎの物真似、犬の遠吠えまで交えて盛り上げました。最後は大曲「たぬき」の後半、息の合ったところを見せてくれました。主任で「住吉踊り」座長の駒三が軽妙な「無精床」で本ワリをしめくくりました。 志ん弥の「湯屋番」に続いて、いつもは一人で高座を勤める小円歌と小菊がコンビで音曲を聴かせます。軽妙な話を挟みながら「夏はうれしや」、「相撲甚句」を唄い、小円歌が「佃の合方」、小菊が「新内流し」を弾くと、楽屋でまねき猫が蛙とこおろぎの物真似、犬の遠吠えまで交えて盛り上げました。最後は大曲「たぬき」の後半、息の合ったところを見せてくれました。主任で「住吉踊り」座長の駒三が軽妙な「無精床」で本ワリをしめくくりました。大喜利の「住吉踊り」を毎年楽しんでいますが、寄席の踊りの集大成という見方で改めて味わってみました。書き留めたメモを頼りに再現してみると、50分を超える内容は次のようになります。 ①伊勢音頭 ②桃太郎 ③奴さん ④長崎さわぎ ⑤さまに逢うとて ⑥風流深川節(深川) ⑦雀踊り ⑧かっぽれ いつもと同じように口開けは「伊勢音頭」です。続いて寄席の踊りでは定番の「桃太郎」、おなじみ「奴さん」が出たところで、座長の駒三が取り持つ「頓智相撲」のやり取りがあって、団扇を持って早い動きの「長崎さわぎ」、次の「さまに逢うとて」は常磐津「勢獅子」の一節です。終盤に差し掛かって、これも定番の「深川」で「ちょき」「駕籠」「坊さま」に加えて市馬作詞・小円歌振付による「お相撲さん」が付きました。今回久しぶりの復活となった「雀踊り」は風流踊りとして江戸時代に大いに流行ったものだそうです。「すずめ踊りが所望じゃが、合点か」「おおさあて、合点だ、アリャセ」の掛け声で、「あごあわせ」という振りを、駒三に志ん陽がからんで大いに笑わせました。最後は締めの「かっぽれ」で今年も目出度くお開きとなりました。 あとがき: 1997年から住吉踊りを毎年欠かさずに見ています。毎回少しずつ新趣向や変化がありますが、基本は変わりません。変らないもの繰り返し見て、なお楽しめるところに芸能の有難さをしみじみとかみしめています。 平成27年8月20日 稲林記
|