|
わたしの寄席: 平成26年八月中席浅草演芸ホール
え〜、お盆吉例の住吉踊り興行、これだけは万障繰り合わせて出かけない訳にはいきません。しかし、今年の夏は暑いですね。上野から地下鉄に乗り継いで田原町から国際通り、雷門通  りの交差点で信号を渡って1本北側の路地(食通街)を抜けて、すし屋通りを左折すると間もなく浅草演芸場の看板が見えてくるのですが、暑さの中を歩くのはくたびれます。開場時刻の10時前に着くと、演芸ホールにはチケットを買う人の長い列が出来ていました。早く来た人は9時前から並んでいたというのですから、寄席通いも元気でなくてはできない仕事です。 りの交差点で信号を渡って1本北側の路地(食通街)を抜けて、すし屋通りを左折すると間もなく浅草演芸場の看板が見えてくるのですが、暑さの中を歩くのはくたびれます。開場時刻の10時前に着くと、演芸ホールにはチケットを買う人の長い列が出来ていました。早く来た人は9時前から並んでいたというのですから、寄席通いも元気でなくてはできない仕事です。住吉踊りが金原亭駒三を座長とする今のかたちになって今年で6年目になりました。落語協会だけでなく芸術協会からも常連の出演者が参加するので、出演者が多く、ダブルキャストになった番組表も住吉踊りならではの賑やかな顔ぶれです。 データ: 平成26年8月13日 浅草演芸ホール 昼の部
入り 開演時 八分 中入 満員 終演時 立見 終演 16:30 コメント: 10時前の開場とともに入場して、しばらくすると前座の小はぜ(柳家)が元気よく「子ほめ」を始めました。翁家社中の太神楽曲芸はいつもは芯になっている和楽の姿がなく、無口(と思われる?)小楽に代って、若い和助が口上を勤めます、前名の桂才紫から今年3月に真打昇進した桂やまとがとぼけた味で「たぬきの札」を演じました。笑組の軽妙な漫才の後、菊之丞の「親子酒」と金時の「なつ泥」ともに個性が出ていた面白く聴きました。最初の中入りの後、にゃんこ金魚が突撃万歳で客席を沸かし、ベテランの圓王は「権助魚」でさらっとした芸を見せてくれます。このあたりの対照が寄席の面白いところです。 中盤に入って、お馴染みの遊平・かほりの夫婦漫才、古今亭菊千代は手話の手ほどきをしながら、めずらしい手話落語を見せてくれました。白酒の演じた「ざる屋」はその昔、先代の馬生(十代目)で聴いたのが耳に残っています。ベテラン花島世津子の手慣れたマジックの後、彦いちのダイナミックな「反対車」で二度目の中入りとなりました。 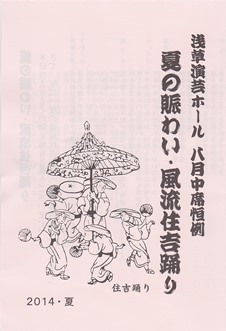 昭和のいる・こいるのこいるが、ひろし・順子の順子先生と組んだ漫才は、こいるの相棒であるのいるが自転車で転んで大けがをしたためということでしたが、お客にとっては思わぬ拾い物の楽しい漫才を見ることが出来ました。爆笑王の歌之介が自伝風の漫談で大いに沸かせ、雷蔵の端正な落語を聴いた後、まねき猫の動物物真似はいつもながら鮮やかです。 昭和のいる・こいるのこいるが、ひろし・順子の順子先生と組んだ漫才は、こいるの相棒であるのいるが自転車で転んで大けがをしたためということでしたが、お客にとっては思わぬ拾い物の楽しい漫才を見ることが出来ました。爆笑王の歌之介が自伝風の漫談で大いに沸かせ、雷蔵の端正な落語を聴いた後、まねき猫の動物物真似はいつもながら鮮やかです。中入り後は常連の志ん弥の漫談のあと、粋曲の小菊と三味線漫談の小円歌がふたりながら高座に登場しての音曲。普段はそれぞれ一人で演じている音曲を二人で掛合いをしながら聴かせるというのは住吉踊り興行ならではのことと思います。「吉原さわぎ」から始めて「おてもやん」「きんらい節」をそれぞれが唄った後、「茄子とかぼちゃ」を唄い、長唄の連れ引きを聴かせました。ふたり三味線ではその昔、昭和50年代の初めころまで寄席に出ていた千家松人形・お鯉という女道楽(三味線音曲)のコンビがいたのを覚えています。 昼の部主任の駒三は「六尺棒」をさらっと演じて大喜利につなげました。 大喜利の「住吉踊り」は今年で36年目になるということを聞きました。毎年少しずつメンバーが入れ替わっているのを時代の流れとして感じていますが、客席と一体になった和の楽しみがこの興行のなによりの魅力です。 あとがき: 自分の記録を調べてみると、1997年から住吉踊りを毎年欠かさずに見ています。その前にも何度か見た記憶がありますが、定かではありません。最大の転機は2001年(平成13年)の住吉踊りを最後にそれまでの座頭、志ん朝師が亡くなったことですが、それから以後も13年続いていのは感慨深いものがあります。個々の芸の出来不出来は別として、芸人さんたちのこの興行にかける思いが自然に伝わってくるようです。 平成26年8月14日 稲林記
|