今月の寄席:
平成18年七月 国立演芸場
 え〜、このところ何かとご縁の深くなった国立演芸場ですが、七月は上席、中席の一挙掲載という快挙で・・、別に大したことはありませんが、お付き合いを願っておきます。
ご存知のように東京の国立劇場には大劇場と小劇場、そしてこの国立演芸場という三つの劇場があります。七月は大劇場で歌舞伎の「彦山権現誓助剣」をやっています。そちらのほうへ声がかかって、久しぶりの大劇場へ行く前に時間があって中入り前まで聴いたのが上席です。
中席は久しぶりにしぶる家人を誘って、暑い中の移動を避けてマイカー出勤という贅沢な寄席通いでした。
データ:その1 え〜、このところ何かとご縁の深くなった国立演芸場ですが、七月は上席、中席の一挙掲載という快挙で・・、別に大したことはありませんが、お付き合いを願っておきます。
ご存知のように東京の国立劇場には大劇場と小劇場、そしてこの国立演芸場という三つの劇場があります。七月は大劇場で歌舞伎の「彦山権現誓助剣」をやっています。そちらのほうへ声がかかって、久しぶりの大劇場へ行く前に時間があって中入り前まで聴いたのが上席です。
中席は久しぶりにしぶる家人を誘って、暑い中の移動を避けてマイカー出勤という贅沢な寄席通いでした。
データ:その1
平成18年七月上席 国立演芸場
H18.7.9
| 演芸 | 出演者 | 演目 | 上がり時刻 |
| 前座 | 三笑亭可女次 | 「饅頭こわい」 | 12:45 |
| 落語 | 三笑亭可龍 | 「片棒」 | 13:01 |
| 曲芸 | 鏡味正二郎 | 建物、傘、まり、茶碗、枡 | 13:18 |
| 落語 | 桂 南なん | 「応挙の幽霊」 | 13:30 |
| 奇術 | 瞳 ナナ | 羽子板、 | 13:50 |
| 落語 | 桂 平治 | 「源平盛衰記」 | 14:06 |
入り 開演時 60% *14:15 途中退出
コメント:
前座の可女次は名前からして、この日の主任、三笑亭可楽のお弟子でしょう。前座にしては大変達者な「饅頭こわい」だった。可龍の「片棒」も面白い、このあたりをウトウトしながら聴いているのが実に気持ちがよい。
聴けた中では南なんの「応挙の幽霊」が時節柄良かった。南なんという芸人さんは、個性的なキャラクターの先入観が強かったが、こうしてじっくりと聴いていると、なんとも良い味わいを持っている。
続いて和風にショウアップされた瞳ナナの一座による本格奇術で目が覚めた後、平治の「源平」半ばにて、後ろ髪を引かれながら演芸場を後にした。
データ:その2
平成18年七月中席 国立演芸場
H18.7.16
| 演芸 | 出演者 | 演目 | 上がり時刻 |
| 前座 | 柳亭市朗 | 「たらちね」 | 12:45 |
| 落語 | 入船亭扇里 | 「子ほめ」 | 13:00 |
| 講談 | 神田香織 |
「山内一豊の妻
出世の馬揃え」 | 13:15 |
| 落語 | 三遊亭吉窓 | 「半分垢」 踊り「ずぼら」 | 13:35 |
| 漫才 | 和才・洋才 |
| 13:55 |
| 落語 | 桂 文楽 | 「看板のピン」 | 14:12 |
| お仲入り |
|
| 14:34 |
| ボーイズ | 玉川カルテット |
| 14:48 |
| 落語 | 初音家左橋 | 「宮戸川」 | 15:05 |
| 俗曲 | 柳家紫文 | 長谷川平蔵シリーズ | 15:24 |
| 主任 | 入船亭扇橋 | 随談と「二人旅」 | 15:42 |
入り 開演時 60% 中入り時 80% 終演時 80%
講談の香織が口跡よくお馴染みの読み物を演じた後、吉窓の「半分垢」は軽妙な一席、それに続けておまけの踊り、吉窓が常連で出演する八月お盆、浅草演芸ホールの「住吉踊り」も近づいていることを思い出した。
和才・洋才の漫才は初めて聴いたが、テンポが良くて面白かった。ベテラン文楽がいつもながらのまくらで客席を笑わした後、これも軽めに「看板のピン」。中入り後の玉川カルテットは浪曲コント。
左橋、紫文に続いて主任で上がった扇橋は、30分あまりの持ち時間の大半を思い出話の随談でつないだ後、得意の二人旅。「どうして」という唄で目出度く締めた。
 あとがき:
国立演芸場の楽しみのひとつが、一階入り口奥の展示室で開催されている展示です。今回はあまりゆっくり見られませんでしたが、展示物の写真だけ撮ってきました。
中に、噺家の配りものの手拭いを展示しているケースを無意識に撮ってきたのをよくみると、なかなかの貴重品です。
左上の桂小南が得意にした「いかけや」を描いた手拭いは大昔にもらって手元にあるものと同じです。「何のいかけと小南に問えばへその茶釜のひび直し」と書いてあったのを覚えています。当時学生だった私は「とかくこの世でしてよいカケは、いかけ、願掛け、命懸け」と書いて小南師匠に送りました。今想うと実に嫌味な若者でした。
真ん中は林家正蔵、これは八代目(稲荷町)でしょう。右下は古今亭志ん朝です。ご興味のある方は写真をクリックして拡大でご覧ください。 あとがき:
国立演芸場の楽しみのひとつが、一階入り口奥の展示室で開催されている展示です。今回はあまりゆっくり見られませんでしたが、展示物の写真だけ撮ってきました。
中に、噺家の配りものの手拭いを展示しているケースを無意識に撮ってきたのをよくみると、なかなかの貴重品です。
左上の桂小南が得意にした「いかけや」を描いた手拭いは大昔にもらって手元にあるものと同じです。「何のいかけと小南に問えばへその茶釜のひび直し」と書いてあったのを覚えています。当時学生だった私は「とかくこの世でしてよいカケは、いかけ、願掛け、命懸け」と書いて小南師匠に送りました。今想うと実に嫌味な若者でした。
真ん中は林家正蔵、これは八代目(稲荷町)でしょう。右下は古今亭志ん朝です。ご興味のある方は写真をクリックして拡大でご覧ください。
平成18年7月17日 稲林記
 ....................... 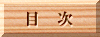 ....................... 
|