今月の寄席:
平成15年八月中席 浅草演芸ホール「住吉踊り」
 え〜、今年も浅草演芸ホールの住吉踊りがやってきました。私が住吉踊りに通うようになったのは1997年(平成9年)です。それから毎年欠かさず、今年で七年、中でも平成十二年には二回行きましたから回数で言うと八回目です。こんなことを言っても、誰もほめる人はおりませんが、自分ひとりで、はあそんなになるかなあと思うだけのことです。あたかも今年は「住吉踊り二十五周年、先代雷門助六十三回忌」といいますから節目の年なのでしょう。先代の助六師が始めた住吉踊りを古今亭志ん朝師が引き継ぎ、いまの金馬師に受け継がれています。先日の「円朝まつり」で今年も踊りの番頭さんを務める三遊亭吉窓さんに「目玉は何ですか?」と訊いたら、「普通にやります」と言っていましたが、そんなものでしょうね。志ん朝師匠晩年の「オーソドックス路線」が今年も継承されています。しかしメンバーは徐々に変っていくようです。
数人の友達としめし合わせて浅草に向かったのですが、朝から生憎の土砂降り、一日中降り続く雨に見舞われてしまいました。この雨では例年に比べて出足がいまひとつかなと思いましたが、前々からこの日に出かけようと心づもりをしていた人も少なくはなかったようです。傘をすぼめるのももどかしく演芸場の中へひとり、また一人と吸い込まれていきます。昨年は前座さんが終わる11時ころには満員でしたが、今年は少し遅れて12時ころ満員になりました。
データ:
え〜、今年も浅草演芸ホールの住吉踊りがやってきました。私が住吉踊りに通うようになったのは1997年(平成9年)です。それから毎年欠かさず、今年で七年、中でも平成十二年には二回行きましたから回数で言うと八回目です。こんなことを言っても、誰もほめる人はおりませんが、自分ひとりで、はあそんなになるかなあと思うだけのことです。あたかも今年は「住吉踊り二十五周年、先代雷門助六十三回忌」といいますから節目の年なのでしょう。先代の助六師が始めた住吉踊りを古今亭志ん朝師が引き継ぎ、いまの金馬師に受け継がれています。先日の「円朝まつり」で今年も踊りの番頭さんを務める三遊亭吉窓さんに「目玉は何ですか?」と訊いたら、「普通にやります」と言っていましたが、そんなものでしょうね。志ん朝師匠晩年の「オーソドックス路線」が今年も継承されています。しかしメンバーは徐々に変っていくようです。
数人の友達としめし合わせて浅草に向かったのですが、朝から生憎の土砂降り、一日中降り続く雨に見舞われてしまいました。この雨では例年に比べて出足がいまひとつかなと思いましたが、前々からこの日に出かけようと心づもりをしていた人も少なくはなかったようです。傘をすぼめるのももどかしく演芸場の中へひとり、また一人と吸い込まれていきます。昨年は前座さんが終わる11時ころには満員でしたが、今年は少し遅れて12時ころ満員になりました。
データ:
平成15年8月15日(昼の部) 浅草演芸ホール
| 演芸 | 出演者 | 演目 | 上がり時刻 |
| 前座 | 入船亭ゆう一 | 「てんしき」 | 10:28開演 |
| 前座 | 柳家り助 | 「子ほめ」 | 10:43 |
| 落語 | 五街道佐助 | 「出来心」 | 10:55 |
| 落語 | 三遊亭吉窓 | 「都々逸親子」 | 11:11 |
| 漫才 | 笑組 |
| 11:25 |
| 落語 | 春雨や雷蔵 | 「八問答」 | 11:34 |
| 落語 | 初音家左橋 | 「酢豆腐」 | 11:44 |
| 落語 | 三遊亭歌る多 | 「穴子でからぬけ」 | 11:55 |
| ものまね | 江戸家まねき猫 | 「河童のいる風景」 | 休憩後 12:13 |
| 落語 | 古今亭菊春 | 「替り目」 | 12:20 |
| 落語 | 三遊亭とん馬 | 「犬の目」 | 12:33 |
| マジック | 花島世津子 | ハンカチ、トランプ、新聞 | 12:42 |
| 落語 | 金原亭駒三 | 「後生うなぎ」 | 12:53 |
| 落語 | 鈴々舎馬風 | 「漫談・海老名家」 | 13:07 |
| ギター漫談 | ペペ桜井 |
| 休憩後 13:21 |
| 落語 | 入船亭扇橋 | 「二人旅」 | 13:30 |
| 落語 | 林家こん平 | 「漫談」 | 13:40 |
| 俗曲 | 三遊亭小円歌 | 「淡海節、見せ物」 | 休憩後 13:55 |
| 落語 | 柳家小せん | 「勘定板」 | 14:07 |
| 落語 | 雷門助六 | 「浮世床」 | 14:19 |
| 漫才 | にゃん子・金魚 |
| 14:35 |
| 落語 | 三遊亭円弥 | 「くやみ」 | 14:48 |
| お仲入り |
|
| 15:03〜 |
| 落語 | 古今亭志ん橋 | 「試し斬り」 | 15:10 |
| 曲芸 | 和楽・小楽・和助 | 傘、ばち、輪投げ | 15:16 |
| 主任 | 三遊亭金馬 | 「四人癖」 | 15:26 |
| 大喜利 | 楽屋総出演 | 住吉踊り | 15:37〜16:35 |
入り:開演時 八割 12時:満員 お仲入り:立見 打ち出し:午後4時35分
コメント:
去年、亭号がわからないと書いた前座のゆう一君がこの日も開口一番。最近入手した2003年版「寄席演芸年鑑」(東京かわら版発行)によれば、扇橋師のお弟子で入船亭ゆう一、と判明した。調べてみたら今年で三年、ゆう一の前座を聴いていることがわかった。当然上達している。二番手の前座、り助は柳家小里ん門下と、これも年鑑で判明した。まるで取り調べのようで恐れ入ります。
二ツ目の佐助は近ごろ、あちこちで活躍が目立つ。「出来心」は昔小さんでよく聴いたオーソドックスな泥棒噺だが、とてもいいテンポで運んでくれた。吉窓の「都々逸親子」は自作か?これも楽しい。にぎやかな笑組の漫才に続いて雷蔵の「八問答」はお目出度い八の字に引っ掛けて強引な問答を展開・・。と、こんな調子で高座はとんとんと進んでいった。
 出演者が多いのでこちらも少し飛ばさせてもらうが、女流の歌る多が与太郎小噺と「穴子」で降りたあと、休憩を挟んで少しスマートになったまねき猫が、新しいネタの「河童」で楽しませてくれた。河童のまねといっても、これは本物を見たことのある人はいないので、どこまでそれらしく演じるかというところだが、河童の気配を感じておびえる犬と猫を配して風景的に描写されたためか、何となく河童を聴いたような気にさせられてしまった。いや、参りました。「大成功」といって自分で喜ぶ花島世津子のほんわかしたマジックの後は駒三の「後生うなぎ」。一種のブラック・ユーモアだが、江戸前の落語の雰囲気で救われる。
二度目の休憩の後のペペ桜井はギターを弾きながら、ハーモニカを吹きながら歌う、という珍芸を披露。扇橋、こん平、小せんといった大ベテランの間にはさまった小円歌も「私もこれで23年目になりました」というから、もう押しも押されもしない芸歴である。この日いちばん迫力を感じたのは高座いっぱいに動き回った「にゃん金」の漫才である。とくに金魚ちゃんの動きは凄いのひとこと。円弥の「くやみ」は思わず故人、六代目円生の話芸を思い出させる。彼がいちばん円生の口調を継承しているのではないかと、終演後に友人と意見が一致した。
大喜利、お待ちかねの「住吉踊り」は小里んと志ん橋の獅子舞で幕が上がった。二頭の獅子の口から「住吉踊り二十五周年」と「先代雷門助六十三回忌」の垂れ幕が出て、踊りがにぎやかに始まる。直前の病気により休演の「ひろし・順子」、毎年出ていた奇術の「美智」先生の顔が見られないのは寂しいが、踊りだけ参加という講談の神田紅さんが初めて姿を見せ、歌る多、右団冶、そしてまねき猫、にゃん・金、世津子、小円歌らの女性の踊り手が大いに盛り上げ、終わってみれば一時間近い「住吉踊り」を今年も十分楽しんだ。
出演者が多いのでこちらも少し飛ばさせてもらうが、女流の歌る多が与太郎小噺と「穴子」で降りたあと、休憩を挟んで少しスマートになったまねき猫が、新しいネタの「河童」で楽しませてくれた。河童のまねといっても、これは本物を見たことのある人はいないので、どこまでそれらしく演じるかというところだが、河童の気配を感じておびえる犬と猫を配して風景的に描写されたためか、何となく河童を聴いたような気にさせられてしまった。いや、参りました。「大成功」といって自分で喜ぶ花島世津子のほんわかしたマジックの後は駒三の「後生うなぎ」。一種のブラック・ユーモアだが、江戸前の落語の雰囲気で救われる。
二度目の休憩の後のペペ桜井はギターを弾きながら、ハーモニカを吹きながら歌う、という珍芸を披露。扇橋、こん平、小せんといった大ベテランの間にはさまった小円歌も「私もこれで23年目になりました」というから、もう押しも押されもしない芸歴である。この日いちばん迫力を感じたのは高座いっぱいに動き回った「にゃん金」の漫才である。とくに金魚ちゃんの動きは凄いのひとこと。円弥の「くやみ」は思わず故人、六代目円生の話芸を思い出させる。彼がいちばん円生の口調を継承しているのではないかと、終演後に友人と意見が一致した。
大喜利、お待ちかねの「住吉踊り」は小里んと志ん橋の獅子舞で幕が上がった。二頭の獅子の口から「住吉踊り二十五周年」と「先代雷門助六十三回忌」の垂れ幕が出て、踊りがにぎやかに始まる。直前の病気により休演の「ひろし・順子」、毎年出ていた奇術の「美智」先生の顔が見られないのは寂しいが、踊りだけ参加という講談の神田紅さんが初めて姿を見せ、歌る多、右団冶、そしてまねき猫、にゃん・金、世津子、小円歌らの女性の踊り手が大いに盛り上げ、終わってみれば一時間近い「住吉踊り」を今年も十分楽しんだ。
あとがき:
住吉踊りのあとは「どぜう」にしようと、かねての手はず(まるで盗賊です)、国際通りを横切って老舗の「飯田屋」で反省の会を催しました。なにしろ、朝の九時半から入場して午後四時半まで椅子に座っていたのですから、座敷に陣取った一同は手足の屈伸をするやら、肩を揉むやら、乾杯のビールでお互いの無事を祝いました。普段はひとりで寄席通いを続けているのですが、こういう仲間との語らいはいいものだと、しみじみ思います。
平成15年8月16日 稲林記

.......................
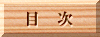
.......................

 え〜、今年も浅草演芸ホールの住吉踊りがやってきました。私が住吉踊りに通うようになったのは1997年(平成9年)です。それから毎年欠かさず、今年で七年、中でも平成十二年には二回行きましたから回数で言うと八回目です。こんなことを言っても、誰もほめる人はおりませんが、自分ひとりで、はあそんなになるかなあと思うだけのことです。あたかも今年は「住吉踊り二十五周年、先代雷門助六十三回忌」といいますから節目の年なのでしょう。先代の助六師が始めた住吉踊りを古今亭志ん朝師が引き継ぎ、いまの金馬師に受け継がれています。先日の「円朝まつり」で今年も踊りの番頭さんを務める三遊亭吉窓さんに「目玉は何ですか?」と訊いたら、「普通にやります」と言っていましたが、そんなものでしょうね。志ん朝師匠晩年の「オーソドックス路線」が今年も継承されています。しかしメンバーは徐々に変っていくようです。
え〜、今年も浅草演芸ホールの住吉踊りがやってきました。私が住吉踊りに通うようになったのは1997年(平成9年)です。それから毎年欠かさず、今年で七年、中でも平成十二年には二回行きましたから回数で言うと八回目です。こんなことを言っても、誰もほめる人はおりませんが、自分ひとりで、はあそんなになるかなあと思うだけのことです。あたかも今年は「住吉踊り二十五周年、先代雷門助六十三回忌」といいますから節目の年なのでしょう。先代の助六師が始めた住吉踊りを古今亭志ん朝師が引き継ぎ、いまの金馬師に受け継がれています。先日の「円朝まつり」で今年も踊りの番頭さんを務める三遊亭吉窓さんに「目玉は何ですか?」と訊いたら、「普通にやります」と言っていましたが、そんなものでしょうね。志ん朝師匠晩年の「オーソドックス路線」が今年も継承されています。しかしメンバーは徐々に変っていくようです。 出演者が多いのでこちらも少し飛ばさせてもらうが、女流の歌る多が与太郎小噺と「穴子」で降りたあと、休憩を挟んで少しスマートになったまねき猫が、新しいネタの「河童」で楽しませてくれた。河童のまねといっても、これは本物を見たことのある人はいないので、どこまでそれらしく演じるかというところだが、河童の気配を感じておびえる犬と猫を配して風景的に描写されたためか、何となく河童を聴いたような気にさせられてしまった。いや、参りました。「大成功」といって自分で喜ぶ花島世津子のほんわかしたマジックの後は駒三の「後生うなぎ」。一種のブラック・ユーモアだが、江戸前の落語の雰囲気で救われる。
出演者が多いのでこちらも少し飛ばさせてもらうが、女流の歌る多が与太郎小噺と「穴子」で降りたあと、休憩を挟んで少しスマートになったまねき猫が、新しいネタの「河童」で楽しませてくれた。河童のまねといっても、これは本物を見たことのある人はいないので、どこまでそれらしく演じるかというところだが、河童の気配を感じておびえる犬と猫を配して風景的に描写されたためか、何となく河童を聴いたような気にさせられてしまった。いや、参りました。「大成功」といって自分で喜ぶ花島世津子のほんわかしたマジックの後は駒三の「後生うなぎ」。一種のブラック・ユーモアだが、江戸前の落語の雰囲気で救われる。