今月の寄席
 え~、今年は梅雨らしい梅雨だなんておだてていたら、天の方も気をよくしたのか、何時まで経ってもじめじめ、うつうつとした空模様が続きます。あんまり天気をほめたり、けなしたりするものではありませんね。晴耕雨読、晴れても降っても「ありがたい」という気持ちをもつようにして・・、それにしても、そろそろ「梅雨明け」といきたいところです。
そんな日々に少し疲れて、久しぶりに上野鈴本へ出かけてみました。
八月のお盆興行も目前ですが、上野鈴本の今月中席夜の部は主任が金原亭馬生です。こんな天気の日にはしみじみとした噺が聴けそうな予感がします。助演の顔ぶれも金原亭一門を中心に楽しみな名前が並んでいます。先日前売り開始と同時に売り切れた今年の「円朝まつり」奉納落語会の第3部は金原亭馬生と兄弟子の五街道雲助のリレー落語で「業平文治」という円朝作品が予定されています。辛うじて前売りを入手したのも馬生を聴きたいためでした。師匠の大きい名前を襲名して4年、これからがいよいよ脂ののるときだと期待しています。
鈴本の前に行ってみると、7~8人ほどの列が出来ていましたが、なんとなく入りは少なそうな感じがしたこの日の夜席、よさそうな席を見つけて荷物をおいてから、売店で飲み物とつまみを買ってじっくりと腰を据えました。鈴本演芸場のホームページに書いてあるように「お弁当を食べてもいいんです。お菓子を食べてもいいんです。ビールを飲んでもいいんです」をそのまま実行しました。
データ:
え~、今年は梅雨らしい梅雨だなんておだてていたら、天の方も気をよくしたのか、何時まで経ってもじめじめ、うつうつとした空模様が続きます。あんまり天気をほめたり、けなしたりするものではありませんね。晴耕雨読、晴れても降っても「ありがたい」という気持ちをもつようにして・・、それにしても、そろそろ「梅雨明け」といきたいところです。
そんな日々に少し疲れて、久しぶりに上野鈴本へ出かけてみました。
八月のお盆興行も目前ですが、上野鈴本の今月中席夜の部は主任が金原亭馬生です。こんな天気の日にはしみじみとした噺が聴けそうな予感がします。助演の顔ぶれも金原亭一門を中心に楽しみな名前が並んでいます。先日前売り開始と同時に売り切れた今年の「円朝まつり」奉納落語会の第3部は金原亭馬生と兄弟子の五街道雲助のリレー落語で「業平文治」という円朝作品が予定されています。辛うじて前売りを入手したのも馬生を聴きたいためでした。師匠の大きい名前を襲名して4年、これからがいよいよ脂ののるときだと期待しています。
鈴本の前に行ってみると、7~8人ほどの列が出来ていましたが、なんとなく入りは少なそうな感じがしたこの日の夜席、よさそうな席を見つけて荷物をおいてから、売店で飲み物とつまみを買ってじっくりと腰を据えました。鈴本演芸場のホームページに書いてあるように「お弁当を食べてもいいんです。お菓子を食べてもいいんです。ビールを飲んでもいいんです」をそのまま実行しました。
データ:
平成15年7月18日 中席夜の部 17時20分開演 上野鈴本演芸場
| 演芸 | 出演者 | 演目 | 備考 |
| 前座 | 柳家初花 | 「子ほめ」 | 17:11 |
| 落語 | 古今亭朝太 | 「元犬」 | 17:25 |
| 粋曲 | 柳家紫文 | 「長谷川平蔵」 | 17:38 |
| 落語 | 三遊亭吉窓 | 「山号寺号」 踊り「大津絵」 | 17:51 |
| 落語 | 古今亭志ん五 | 「素人鰻」 | 18:04 |
| 落語 | 初音家左橋 | 「酢豆腐」 | 18:18 |
| 漫才 | 大瀬ゆめじ・うたじ | 「わりばし」 | 18:31 |
| 落語 | 柳亭燕路 | 「締め込み」 | 18:46 |
| 落語 | 金原亭伯楽 | 「あくび指南」 | 19:06 |
| お仲入り |
|
| 19:22 |
| 奇術 | アサダ二世 | ハンカチ、ロープほか | 19:29 |
| 落語 | 吉原朝馬 | 「六尺棒」 | 19:44 |
| 落語 | 三遊亭歌武蔵 | 「大安売り」 | 20:00 |
| 太神楽曲芸 | 鏡味仙三郎社中 | 傘、建物、まり他 | 20:16 |
| 主任 | 金原亭馬生 | 「茶金」 | 20:27 |
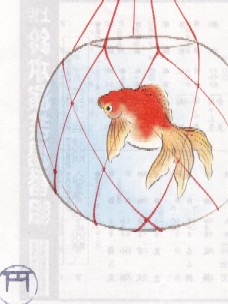 入り:開演時 2割 仲入り時 3割 終演時 3割 打ち出し:21時00分
入り:開演時 2割 仲入り時 3割 終演時 3割 打ち出し:21時00分
コメント:
「古今亭朝太」という名前は何代目でしょうか。亡き志ん朝師が売り出してきた前座、二つ目時代の名前としての印象がいちばん強いのですが、その後では今の志ん輔が二つ目時代に名乗っていたのを覚えています。古くは五代目古今亭志ん生の前座名が三遊亭朝太であったことに由来すると思われる古今亭一門の出世名のようです。いまの二つ目、朝太は黒紋付のすっきりした姿で「元犬」を一席伺っていました。
粋曲の紫文は得意の「長谷川平蔵」シリーズ。三味線をバックにオムニバス風のコントをつないでゆくのですが、つなぎに入れる間奏がいろいろな曲を聴けるので飽きません。この日は①納豆屋、②とんがらし屋、③宅配屋、④蕎麦屋、⑤葬儀屋の順でした。初めて聴いたのは「とんがらし屋」で、「とんがらし屋さん怪我はなくって?」、「へい、お蔭さまで怪我はありませんが、七色とんがらしが十二色になってしまいました」、「どうしてだい?」、「へー、転んだ拍子にゴミ(五味)が入りましたから」。こう書いてみると、それほど面白くはない? 吉窓の踊り、大津絵の「吃又(どもまた)」は来月の住吉踊りの稽古でしょうか。
志ん輔の代演で登場した志ん五の出囃子がいつもの「芸者ワルツ」ではなくて長唄「藤娘」に変っていたのは心境の変化でしょうか?「素人鰻」がとぼけた味で可笑しかったです。続いて金原亭一門の左橋は酢豆腐を13分で演じました。こういうところがプロの大胆さでしょう。時間は短かったけれど「若旦那」が面白かった。うんちく漫才のゆめじ・うたじの「わりばし」は新ネタか?柳亭燕路の「締め込み」は上等。とくにおかみさんが亭主との馴れ初めをしゃべりながら夫婦喧嘩するところ、泥棒が仕方なく仲裁にでてくるところがなんとも言えない面白さで、「締め込み」という演題の由来がわかる最後の落ちまでを演じました。仲入りの伯楽も夏らしい「あくび指南」。「酢豆腐」と「あくび指南」、先月見沼くらしっく館でやった噺が二つとも出たのでびっくりしました。当然ですが、プロはぜんぜん違います。
お仲入りが過ぎても、客足が一向に伸びません。小人(こびと:入りがすくないこと)の席はゆったりしていてよいのですが、こう客足が伸びないと、出演者に済まないような気になります。アサダ二世のおとぼけ手品のあとは、いかにも芸人らしい朝馬の「六尺棒」。噺の中で親父が道楽息子に小言をいうところで、「お隣の佐竹さんの守さんを少しは見習ったらどうだ」と言ったのはまったくの楽屋落ちで、この日の主任、現馬生の本名(佐竹守)を引き合いに出していました。この手の楽屋落ちはしばしば出てくるものです。大相撲出身の歌武蔵が相撲ネタの「勝ったり負けたり」(相手が勝ったり、こっちが負けたり)の演題を「『大安売り』というお笑いで・・・」と言って降りたので、そういう名前の噺なのかと初めて分かりました。
仙三郎社中の太神楽の後は、お目当て、主任の馬生。短い前置きの後、さっとまくらを振って「はてなの茶碗」の別名でも知られる「茶金」に入っていきました。京都が舞台で、主人公の江戸っ子、八五郎のほかはすべて京言葉で噺が進んでいきます。骨董の目利き、茶屋金次郎が器を見て、「はてな」と首をひとつひねると、百両の価値が出ると言う。勘違いから端を発したはなしは思わぬ展開となり、清水寺の茶店の駄茶碗に千両の値がついてしまいます。味をしめた八っつぁんが、大きな水がめを担いでくる落ちに江戸っ子らしい稚気が感じられて、後味の良い噺でした。
あとがき:
この夜の主任、馬生のところでハプニングがありました。まくらを話しているときに、前の方の席にいたお年寄りがふいと立ち上げって帰りかけたのを高座から馬生が「お帰りになるんですか?私ひとりで終わりになります。せっかくですから、お急ぎでなかったら聴いていっていただけませんか」と声をかけました。「はあ、そうですか。それでは聴かせてもらいます」と言って座りなおしたお爺さんに客席から拍手がおこりました。馬生のほうは「本当に大丈夫ですか。すいません」と言って、また噺に戻っていきました。この日の入りはそのくらい寂しかったのですが、真打の噺をきっちりと聴いて、得した気分で「デテケ、デテケ、デテケ・・・・」の追い出し太鼓を背に広小路へ出ました。(右上の挿絵は上野鈴本演芸場七月中席プログラム表紙から借用しました)
平成15年7月19日 稲林記

.......................
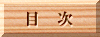
.......................

 え~、今年は梅雨らしい梅雨だなんておだてていたら、天の方も気をよくしたのか、何時まで経ってもじめじめ、うつうつとした空模様が続きます。あんまり天気をほめたり、けなしたりするものではありませんね。晴耕雨読、晴れても降っても「ありがたい」という気持ちをもつようにして・・、それにしても、そろそろ「梅雨明け」といきたいところです。
え~、今年は梅雨らしい梅雨だなんておだてていたら、天の方も気をよくしたのか、何時まで経ってもじめじめ、うつうつとした空模様が続きます。あんまり天気をほめたり、けなしたりするものではありませんね。晴耕雨読、晴れても降っても「ありがたい」という気持ちをもつようにして・・、それにしても、そろそろ「梅雨明け」といきたいところです。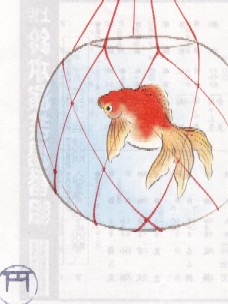 入り:開演時 2割 仲入り時 3割 終演時 3割 打ち出し:21時00分
入り:開演時 2割 仲入り時 3割 終演時 3割 打ち出し:21時00分