今月の寄席
平成14年12月(追加編) 末広亭余一会
 12月、年の暮れの楽しみはこのところ毎年寄席の聴き納めにしている新宿末広亭の「さん喬・権太楼二人会」です。昨年は1時間以上前に駆けつけて並んだのですが、今年は1階席を指定前売りすると聞きつけ、発売日の12月1日(日)正午を目指して新宿へ行きました。11時半に末広亭前に着いたときには既に販売が始まっていてようやく買えたのは下手桟敷の後ろ席。それでも私のあとは5枚くらいしか残っていないと聞けば、自分の幸運を喜ばずにはいられないという、何だか大変なことになってきました。そうやって手に入れた2枚の指定券の有難さを十分に言い聞かせて、勿体をつけて家人を誘い暮れの街へ飛び出しました。当日売りに並ぶ長蛇の列をなんだか済まないような気持ちで通り過ぎてお約束の席に陣取り、伊勢丹の地下で買ったお弁当など食べているうちに、とうとう当日売りの2階席もいっぱいになって、立見が出始めたところで前座さんか高座に現れました。
どうして、こんなに人気があるのでしょうか。さん喬、権太楼の両師匠が実力派の中堅であることは間違いありませんが、それだけではなく、お客さんを集めて大いに喜ばせる努力をしているのです。この日も、私たちが末広亭に着いたとき、前の道端で権太楼の一門の弟子達がカレンダーと林檎を売っています。さくらの客の趣向であれこれ尋ねているのが権太楼師本人でした。出店を片付けに掛かったところのスナップをデジカメで撮ったときに権太楼師と目が合ってしまいました。上の写真がそれです。フラッシュが弱くて分かりにくいのですが、真中のバッグを首から掛けているのが権太楼師でした。
データ:
12月、年の暮れの楽しみはこのところ毎年寄席の聴き納めにしている新宿末広亭の「さん喬・権太楼二人会」です。昨年は1時間以上前に駆けつけて並んだのですが、今年は1階席を指定前売りすると聞きつけ、発売日の12月1日(日)正午を目指して新宿へ行きました。11時半に末広亭前に着いたときには既に販売が始まっていてようやく買えたのは下手桟敷の後ろ席。それでも私のあとは5枚くらいしか残っていないと聞けば、自分の幸運を喜ばずにはいられないという、何だか大変なことになってきました。そうやって手に入れた2枚の指定券の有難さを十分に言い聞かせて、勿体をつけて家人を誘い暮れの街へ飛び出しました。当日売りに並ぶ長蛇の列をなんだか済まないような気持ちで通り過ぎてお約束の席に陣取り、伊勢丹の地下で買ったお弁当など食べているうちに、とうとう当日売りの2階席もいっぱいになって、立見が出始めたところで前座さんか高座に現れました。
どうして、こんなに人気があるのでしょうか。さん喬、権太楼の両師匠が実力派の中堅であることは間違いありませんが、それだけではなく、お客さんを集めて大いに喜ばせる努力をしているのです。この日も、私たちが末広亭に着いたとき、前の道端で権太楼の一門の弟子達がカレンダーと林檎を売っています。さくらの客の趣向であれこれ尋ねているのが権太楼師本人でした。出店を片付けに掛かったところのスナップをデジカメで撮ったときに権太楼師と目が合ってしまいました。上の写真がそれです。フラッシュが弱くて分かりにくいのですが、真中のバッグを首から掛けているのが権太楼師でした。
データ:
平成14年12月29日 17時30分開演 新宿末広亭
| 演芸 | 出演者 | 演目 | 備考 |
| 前座 | 柳家さん市 | 「牛ほめ」 | 17:30 |
| 落語 | 柳家小権太 | 「初天神」 | 17:40 |
| 落語 | 柳家喬四郎 | 「浮世床」 | 18:00 |
| 太神楽曲芸 |
翁家和助
鏡見仙三 | ばち、建もの、傘 | 18:15 |
| 落語 | 柳家さん喬 | 「穴泥」 | 18:30 |
| 落語 | 柳家権太楼 | 「井戸の茶碗」 | 19:02 |
| お仲入り |
|
| 19:40 |
| 奇術 | 花島世津子 | ハンカチ、カードほか | 20:05 |
| 落語 | 柳家権太楼 | 「寝床」 | 20:20 |
| 落語 | 柳家さん喬 | 「鰍沢」 | 20:50 |
入り:開演時 満員 仲入り時 満員 終演時 満員 打ち出し:21時35分
コメント:
開口一番で登場した前座はさん喬一門のさん市、開演直前まで客席で師匠のCDを売っていた。思わず「可哀相な落語家に愛の灯を!」と叫んでしまい、「師匠がかわいそうだってえのか?」と兄弟子からどやされながらも、なんとか完売に漕ぎ着けていました。ご苦労様!と言ってあげたいです。年末に二つ目になった小権太の「初天神」、喬四郎の「浮世床」(芝居見物)に続く最初の色物は変ったコンビの太神楽。翁家和楽社中の和助と鏡見仙三郎社中の仙三が組んでのコント風太神楽でした。あとに上がったさん喬師の説明によれば、ふたりは第1期太神楽研修生の同期だそうです。この珍妙なコンビを高座に上げたのは若い二人をお客様に覚えてもらおうとの楽屋の暖かい配慮があったのでしょう。
さて、最初のお目当て、さん喬の「穴泥」は年末落語の定番です。押し詰まって三両の金が工面出来ず、女房からどやされて表へ飛び出した男が、大店の裏座敷に紛れ込んで宴会の残り物を飲み食いして酔っぱらってしまい、這ってきた赤ん坊をあやしているうちに防火用の穴倉のふたがずれていたところへ落っこちて大騒ぎになる噺です。至急呼び出されてきた、町内の頭の居候で「横浜の向こう見ずのテツ」という頼りない兄いと穴の中の泥棒のやり取りがなんとも可笑しく、大店の主人の寛容さが耳に心地よい、年の暮らしい落語を聞かせてもらいました。続く権太楼の「井戸の茶碗」も善人ばかりが登場します。千代田朴斎という浪人と細川家の若侍、その間に立つ屑屋の清兵衛さん、三者三様の一徹さから生まれる笑いを権太楼が個性豊かにみっちりと演じました。
 仲入り後は、美人(本人がそう言っていた)手品師の花島(はなじま)世津子。軽妙な語りで「あれあれあれ・・」といつも楽しく見せる手品です。二人会の前半後半の間に挟まれて、場内の雰囲気を整えてくれる色物の良さを毎回感じます。
権太楼の二席目は「寝床」、これまた爆笑編で大いに沸きました。この寝床という落語は下手な浄瑠璃を無理やり聞かされる側の辛さが強調されすぎており、義太夫好きの私としては「そんなに悪く言わなくてもいいだろうに」と思うときもありますが、カラオケなどで息苦しくなるような唄を聞かされることはよくあるので、「芸の押し付けは良くない」戒めとして末永く語り継がれる教訓落語?でしょう。権太楼の演出は古今亭志ん生系で、長屋の衆が集まって相談する中で登場する、以前お店にいた評判の良い番頭さんが旦那の義太夫に耐えかねて出奔してしまうくだりの熱演に亡くなった志ん朝師の「寝床」を思い出しました。
替わってさん喬の主任ネタ「鰍沢」は冬に演じられることの多い人情噺で、三遊亭円朝がお客から三つの題をもらって作った三題噺の傑作です。雪の中で道に迷った旅人が一夜の宿を頼んだ山家の一軒屋で偶然再会したもと吉原の花魁「月の輪のお熊」に懐の金目当てに毒入りの玉子酒を飲まされ、後で帰ってきた猟人の亭主が残りの玉子酒を飲んで苦しむのを寝床で聞いて雪の中を逃げ出す後ろから、夫の仇とお熊が火縄銃を持って追いかけてゆく・・。月明かりに照らされた一面の雪景色の中を熊野の毒消しの札を飲んでようよう逃げる旅人と追いついて狙いを定める月の輪のお熊、鰍沢の断崖から雪とともに滑り落ち、つないであった筏(いかだ)とともに流されながら「南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経・・・・」と一心にお題目を唱える後ろから鉄砲の音、ほおをかすめて前の岩に弾が「カチリ」・・。迫真の描写をみせるさん喬の話芸には冴えがありました。
あとがき:
12月の末広亭最終日(29日)の余一会に通うようになって、年末の楽しみが増えました。発売と同時に売り切れた1階の240席に座っていたお客さんは皆、同じ気持ちで前売りを買ったのでしょう。年配者、夫婦連れが目立ちました。相次ぐ熱演のために、予定の午後9時を40分近くオーバーしてハネた末広亭を今年1年の寄席通いの感慨とともに後にして、歳末の人出でごった返す新宿駅を目指しました。
仲入り後は、美人(本人がそう言っていた)手品師の花島(はなじま)世津子。軽妙な語りで「あれあれあれ・・」といつも楽しく見せる手品です。二人会の前半後半の間に挟まれて、場内の雰囲気を整えてくれる色物の良さを毎回感じます。
権太楼の二席目は「寝床」、これまた爆笑編で大いに沸きました。この寝床という落語は下手な浄瑠璃を無理やり聞かされる側の辛さが強調されすぎており、義太夫好きの私としては「そんなに悪く言わなくてもいいだろうに」と思うときもありますが、カラオケなどで息苦しくなるような唄を聞かされることはよくあるので、「芸の押し付けは良くない」戒めとして末永く語り継がれる教訓落語?でしょう。権太楼の演出は古今亭志ん生系で、長屋の衆が集まって相談する中で登場する、以前お店にいた評判の良い番頭さんが旦那の義太夫に耐えかねて出奔してしまうくだりの熱演に亡くなった志ん朝師の「寝床」を思い出しました。
替わってさん喬の主任ネタ「鰍沢」は冬に演じられることの多い人情噺で、三遊亭円朝がお客から三つの題をもらって作った三題噺の傑作です。雪の中で道に迷った旅人が一夜の宿を頼んだ山家の一軒屋で偶然再会したもと吉原の花魁「月の輪のお熊」に懐の金目当てに毒入りの玉子酒を飲まされ、後で帰ってきた猟人の亭主が残りの玉子酒を飲んで苦しむのを寝床で聞いて雪の中を逃げ出す後ろから、夫の仇とお熊が火縄銃を持って追いかけてゆく・・。月明かりに照らされた一面の雪景色の中を熊野の毒消しの札を飲んでようよう逃げる旅人と追いついて狙いを定める月の輪のお熊、鰍沢の断崖から雪とともに滑り落ち、つないであった筏(いかだ)とともに流されながら「南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経・・・・」と一心にお題目を唱える後ろから鉄砲の音、ほおをかすめて前の岩に弾が「カチリ」・・。迫真の描写をみせるさん喬の話芸には冴えがありました。
あとがき:
12月の末広亭最終日(29日)の余一会に通うようになって、年末の楽しみが増えました。発売と同時に売り切れた1階の240席に座っていたお客さんは皆、同じ気持ちで前売りを買ったのでしょう。年配者、夫婦連れが目立ちました。相次ぐ熱演のために、予定の午後9時を40分近くオーバーしてハネた末広亭を今年1年の寄席通いの感慨とともに後にして、歳末の人出でごった返す新宿駅を目指しました。
平成14年12月31日 稲林記

.......................
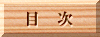
.......................

 12月、年の暮れの楽しみはこのところ毎年寄席の聴き納めにしている新宿末広亭の「さん喬・権太楼二人会」です。昨年は1時間以上前に駆けつけて並んだのですが、今年は1階席を指定前売りすると聞きつけ、発売日の12月1日(日)正午を目指して新宿へ行きました。11時半に末広亭前に着いたときには既に販売が始まっていてようやく買えたのは下手桟敷の後ろ席。それでも私のあとは5枚くらいしか残っていないと聞けば、自分の幸運を喜ばずにはいられないという、何だか大変なことになってきました。そうやって手に入れた2枚の指定券の有難さを十分に言い聞かせて、勿体をつけて家人を誘い暮れの街へ飛び出しました。当日売りに並ぶ長蛇の列をなんだか済まないような気持ちで通り過ぎてお約束の席に陣取り、伊勢丹の地下で買ったお弁当など食べているうちに、とうとう当日売りの2階席もいっぱいになって、立見が出始めたところで前座さんか高座に現れました。
12月、年の暮れの楽しみはこのところ毎年寄席の聴き納めにしている新宿末広亭の「さん喬・権太楼二人会」です。昨年は1時間以上前に駆けつけて並んだのですが、今年は1階席を指定前売りすると聞きつけ、発売日の12月1日(日)正午を目指して新宿へ行きました。11時半に末広亭前に着いたときには既に販売が始まっていてようやく買えたのは下手桟敷の後ろ席。それでも私のあとは5枚くらいしか残っていないと聞けば、自分の幸運を喜ばずにはいられないという、何だか大変なことになってきました。そうやって手に入れた2枚の指定券の有難さを十分に言い聞かせて、勿体をつけて家人を誘い暮れの街へ飛び出しました。当日売りに並ぶ長蛇の列をなんだか済まないような気持ちで通り過ぎてお約束の席に陣取り、伊勢丹の地下で買ったお弁当など食べているうちに、とうとう当日売りの2階席もいっぱいになって、立見が出始めたところで前座さんか高座に現れました。 仲入り後は、美人(本人がそう言っていた)手品師の花島(はなじま)世津子。軽妙な語りで「あれあれあれ・・」といつも楽しく見せる手品です。二人会の前半後半の間に挟まれて、場内の雰囲気を整えてくれる色物の良さを毎回感じます。
仲入り後は、美人(本人がそう言っていた)手品師の花島(はなじま)世津子。軽妙な語りで「あれあれあれ・・」といつも楽しく見せる手品です。二人会の前半後半の間に挟まれて、場内の雰囲気を整えてくれる色物の良さを毎回感じます。