見たり聴いたり:
段数 | 場名 | 通称 |
| 大序 | 鶴ヶ岡社頭兜改めの場 | 兜改め |
| 二段目 | 桃井館の場 | 松きり |
| 三段目 |
足利館門前進物の場 同 松の間刃傷の場 同 裏門の場 | 喧嘩場 |
| 四段目 |
扇ケ谷塩冶判官切腹の場 同 表門城明渡しの場 道行 旅路の花聟 | 判官切腹 |
| 五段目 |
山崎街道鉄砲渡しの場 同 二つ玉の場 | 山崎街道 |
| 六段目 | 与市兵衛内勘平腹切の場 | 勘平腹切 |
| 七段目 | 祇園一力茶屋の場 | 茶屋場 |
| 八段目 | 道行 旅路の嫁入 | |
| 九段目 | 山科閑居の場 | 山科閑居 |
| 十段目 | 天川屋の場 | |
| 十一段目 |
高家表門討入りの場 同 奥庭泉水の場 同 炭部屋本懐の場 | 討入り |
 「二つ玉」の前の短い場面ですが、続いて起こる六段目の悲劇にいたる伏線として大事なところです。下座の太鼓による雨音で幕が開くと猟人姿の早野勘平が雨宿りという格好で木の下に佇んでいます。浄瑠璃につれて顔を隠していた笠を除ける瞬間の間と姿のよさが歌舞伎の瞬間美。そんな言葉があるかどうか知りませんが、芝居を見る楽しさがここに凝縮していると私は思っています。にわかの雨で火縄を消してしまった勘平が夜の山中を通りかかった侍に声を掛けて提灯の火をねだる、用心する侍に鉄砲を預けようと提灯の火に顔を近づけると、「和殿は早野勘平ならずや」、「さ言うは弥五郎殿」、「まずは堅固で」、「貴殿もご無事で」と交わす言葉は侍仲間。塩谷の遺臣同志が偶然出会った雨夜の闇の深さが次の場の伏線となります。
「二つ玉」の前の短い場面ですが、続いて起こる六段目の悲劇にいたる伏線として大事なところです。下座の太鼓による雨音で幕が開くと猟人姿の早野勘平が雨宿りという格好で木の下に佇んでいます。浄瑠璃につれて顔を隠していた笠を除ける瞬間の間と姿のよさが歌舞伎の瞬間美。そんな言葉があるかどうか知りませんが、芝居を見る楽しさがここに凝縮していると私は思っています。にわかの雨で火縄を消してしまった勘平が夜の山中を通りかかった侍に声を掛けて提灯の火をねだる、用心する侍に鉄砲を預けようと提灯の火に顔を近づけると、「和殿は早野勘平ならずや」、「さ言うは弥五郎殿」、「まずは堅固で」、「貴殿もご無事で」と交わす言葉は侍仲間。塩谷の遺臣同志が偶然出会った雨夜の闇の深さが次の場の伏線となります。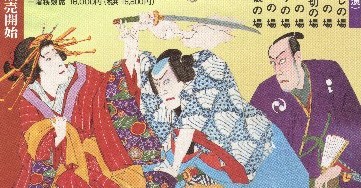 4.七段目 祇園一力茶屋の場
4.七段目 祇園一力茶屋の場実名 | 役職 | 役名 | 役名(よみがな) |
| 浅野内匠頭長矩 | 播州赤穂城主 | 塩谷判官高定 | えんやはんがんたかさだ |
| 大石内蔵助 | 筆頭国家老 | 大星由良之助 | おおぼしゆらのすけ |
| 大石 力 | 内蔵助長男 | 大星力弥 | おおぼしりきや |
| 萱野三平 | 浅野家臣 | 早野勘平 | はやのかんぺい |
| 寺坂吉右衛門 | 足軽 | 寺岡平右衛門 | てらおかへいえもん |
| 大野九郎兵衛 | 城代家老 | 斧九太夫 | おのくだゆう |
| 神崎与五郎 | 浅野家臣 | 千崎弥五郎 | せんざきやごろう |
| 梶川与惣兵衛 | 大奥留守居番役 | 加古川本蔵 | かこがわほんぞう |
| 吉良上野介義央 | 高家筆頭 | 高 師直 | こうのもろなお |