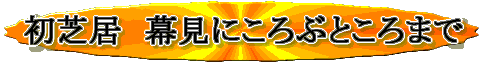
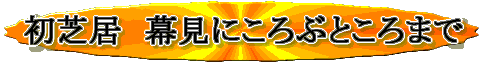
 はじめに:
はじめに:|
歌舞伎座にしかない「1幕見席」(歌舞伎座の看板より)
「1幕見席」は昔から芝居通の席といわれ、好きな幕を何回もみるかた、一寸の時間を割いて芝居を楽しむかたに喜ばれ賑ってきました。いまはもうこの歌舞伎座にしか残っておりません。幕見席は評判の一幕、お好きな狂言を繰返し見るのにはなんと言っても安くて便利です。一時間か二時間の短い時間で映画よりも安い料金で、芝居の豊かな雰囲気の中にひたることは、今の忙しい時間に又とない心の休息所ともいえましょう。 |
御観劇料 |
|
| 一等席 | 15,000円(税共15,750円) |
| 二等席 | 10,000円(税共10,000円) |
| 三階A席 | 4,000円(税共 4,200円) |
| 三階B席 | 2,400円(税共 2,520円) |
| 一階桟敷 | 16,000円(税共16,800円) |
昼の部 |
||
| 鞘當 | 11:00〜11:20 | 900円 |
| 連獅子 | 11:30〜12:25 | |
| 妹背山婦女庭訓・吉野川 | 12:55〜15:00 | 1000円 |
| さくら川 | 15:20〜16:00 | 600円 |
夜の部 |
||
| 一谷嫩軍記・熊谷陣屋 | 16:30〜17:55 | 900円 |
| 春興鏡獅子 | 18:30〜19:25 | 800円 |
| 人情噺文七元結 | 19:45〜20:55 | 800円 |
 歌舞伎座は有楽町から晴海通りを進み銀座4丁目の交差点を渡ってさらに昭和通りの三原橋交差点を渡った左側にあります。そのくらい知ってるよ、っていうかたがほとんどでしょうね。左の写真のような特徴のある建物ですからすぐわかります。
歌舞伎座は有楽町から晴海通りを進み銀座4丁目の交差点を渡ってさらに昭和通りの三原橋交差点を渡った左側にあります。そのくらい知ってるよ、っていうかたがほとんどでしょうね。左の写真のような特徴のある建物ですからすぐわかります。 歌舞伎座正面に向かって左が「幕見」専用の「御入口」です。右の写真では開演中で扉が閉まっていますが、押せば開きます。入口が別だということ忘れないで下さい。それから紛らわしいのが、右の写真の左奥に赤い毛氈の長床机があって、そのあたりに座ってあるいはそのつづきに立って並んでいる人たちがいることがあります。それは新聞社などからの招待券や割引券で入場する人たちですからまがえないで下さい。前の幕が終わるまでは通常右の写真の入口を入って切符売り場の前に並んで待ちます。
歌舞伎座正面に向かって左が「幕見」専用の「御入口」です。右の写真では開演中で扉が閉まっていますが、押せば開きます。入口が別だということ忘れないで下さい。それから紛らわしいのが、右の写真の左奥に赤い毛氈の長床机があって、そのあたりに座ってあるいはそのつづきに立って並んでいる人たちがいることがあります。それは新聞社などからの招待券や割引券で入場する人たちですからまがえないで下さい。前の幕が終わるまでは通常右の写真の入口を入って切符売り場の前に並んで待ちます。 格好の場と心得てゆっくりゆっくり上っていきます。天国に続くのではないかと思うこともあるこの階段が「幕見」の唯一・最大の障壁ですが、黙々と上っていく姿には求道者のような尊さを感じます。「ひとの一生は重荷を背負って遠い道を歩くがごとし」という東照神君・家康公の教えも頭をよぎることがあります。まあ、それほどでもありませんが。
格好の場と心得てゆっくりゆっくり上っていきます。天国に続くのではないかと思うこともあるこの階段が「幕見」の唯一・最大の障壁ですが、黙々と上っていく姿には求道者のような尊さを感じます。「ひとの一生は重荷を背負って遠い道を歩くがごとし」という東照神君・家康公の教えも頭をよぎることがあります。まあ、それほどでもありませんが。