見たり聴いたり:
え〜、芝居や演芸を観たり聴いたりするのも、これでご縁がつきものですね。むずかしく言えば一期一会の連続のようなものです。今回の柳家小のぶ独演会がまさにそれでした。 きっかけは我が家のリフォームで発掘したガリ版刷り(なんとなつかしい)のパンフレットでした。下の縮刷版で表題「柳家小のぶ独演会を聴く」の文字が読み取れると思いますが、左下に「昭和59年十月十八日六時半より、於 本牧亭」とありますから、平成二年に閉じた上野広小路の本牧亭で二十年前に開かれた独演会の記録です。  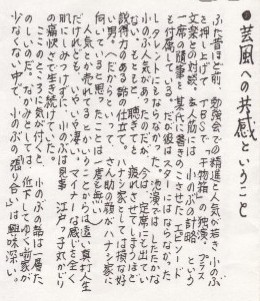 もう少し、当時のコメントを眺めてみましょう。右にやや拡大した「芸風への共感ということ」のなかには もう少し、当時のコメントを眺めてみましょう。右にやや拡大した「芸風への共感ということ」のなかには二十代にして世に出た小のぶが玄人筋の評価を得ながらもスターやタレントにはならず、これが書かれた二十年前、すでに定席の寄席に出ていないこと、それでいて根強いファンを感動させて生き続けていることへの共感がつづられています。 「人気とか売れているとかいうことからは遠い真打人生だけれども、いやいや凄い。マイナーな感じを全く肌にしみつけずに、小のぶは見事江戸っ子丸かじりの痛快さで生き続けていた」という。 それからさらに二十年が経って、いまはどんな風に落語を演じてているのか・・・急に小のぶを聴いてみたいと思いました。 柳家小のぶを聴くことはできるのか、と手元の演芸情報誌「東京かわら版」をめくると3月26日(金)さいたま市民会館うらわ四階和室にて「柳家小のぶ独演会」という予告が出ているではありませんか。「さいたま市民会館うらわ」なんて変な名前になってますが、さいたま市合併前の「浦和市民会館」です。余談ですが、ここのホールでは三遊派旗揚げ直後に弟子達とともに各地を回っていた六代目圓生の「文違い」を聴いたことがあります。浦和で小のぶが聴ける、迷わず出かけました。 データ: 平成十六年三月二十六日 さいたま市浦和市民ホール
終演 20:50 落語の本題に入る前、まくらの中で噺の中に出てくる川柳や戒めの言葉の意味をそれとなく解説してくれるのが小のぶ落語のパターンです。一席目「風呂敷」では「瓜田に靴をぬがず」、「李下に冠をかぶらず」、「貞女両夫にまみえず」・・など、つぎつぎに説明を聞いていると、噺の中の飄逸なくすぐりが思い出されてつい笑いがこみ上げてきます。間男まがいの事態を引き起こして駆け込んでくる女房、それを珍妙な教訓で諭す兄い、泥酔して押入の前に居座る亭主、それぞれがくっきりと息づいています。 二席目は「子別れ」の下(げ)である「子は鎹(かすがい)」。ここでも噺の中に出てくる小道具の玄翁(げんのう)と金槌の違いが分かりやすく説明されます。木と木をつなぐ「かすがい」を打つのは金槌ではなく、やや大きめの玄翁でなくてはならないという。人情噺の味わいを持つ「子別れ」の下をこれも丁寧な運びで、ひとりひとりの人物を描き分け、目の前でドラマが展開されて行く臨場感が味わえました。この夜の三席の中でも特に出色であったと思います。 短い休憩をはさんで三席目の「蒟蒻(こんにゃく)問答」。この噺こそ、懇切な解説を聴けることを期待したのですが、開演が遅れたことによる制約があったようで、小のぶ師匠自身も「時間がありませんので」と断って比較的短い前置きで噺に入っていきました。「法海に魚あり、尾もなく頭もなく、中の四骨を絶つ」なんて、きっと解説の用意があったことでしょう。蒟蒻問答という噺はきちっと情景を描ける話芸の力がないとつらいことになりますが、当然ここは小のぶ落語の真骨頂で後半の問答の部分は一画もゆるがせにしない芸の気配りを見せてくれました。 以上三席を聴いて、「小のぶ落語」の文脈に改めて気づかされました。それはひとくちで言って「古風だがパワーのある落語」を誠実に聴かせてくれる真面目な芸であるということです。最近の寄席に通い続けていて、ときどき感じる空虚な想いはなんなのか。寄席興行の流れの中でサラサラと目の前を通り過ぎて行く芸人達。その身軽さもそれほど悪いものではないけれど、ぐっと踏ん張る歯ごたえのある芸はひと芝居(興行)でひとりかふたり、あとは全体のバランスに乗っかったチームプレイ(団体競技?)がよくも悪くも寄席の特徴になっています。小のぶという芸人の誠実さ、よい意味での不器用さが寄席には合わない。やるからにはいつも全力投球したい芸人にとっては今回のような独演会がふさわしいのでしょう。久しぶりに落語という芸の原点に思いをはせることの出来た貴重な会でした。 あとがき:
現在、柳家小のぶ師は独演会を中心に公演を行なっているようです。今回ご紹介した浦和での会もそのひとつです。各地に根強い支持者がいて、定期的な巡回独演会を催していることが分かりました。次の浦和での独演会は一年先かもしれませんが、また聴いてみたいと思います。 平成16年4月16日 稲林記
|