見たり聴いたり:
磯山 雅氏の著書とともに カール・リヒター指揮によるJ.S.Bachの《ヨハネ受難曲》(1964年録音)を入手したのは1998年でした。それから20年以上の歳月が流れています。同じころ、著書を読み、ご講演をお聴きすることもあった(後述します)音楽学者の磯山 雅(いそやまただし)氏から貴重な教示をいただきました。その磯山氏が三年前に急逝されたのは大変残念なことです。 磯山氏の遺著、「ヨハネ受難曲」(筑摩書房 2020年1月)を最近入手することが出来ました。遺された記述をたどりながら、いま改めてリヒターの《ヨハネ受難曲》を鑑賞しています。 1.リヒターの《ヨハネ受難曲》 磯山 雅氏解説より リヒター指揮(演奏:ミュンヘン・バッハ管弦楽団、合唱:ミュンヘン・バッハ合唱団)の《ヨハネ受難曲》CDブックレットに収録された解説の書き出し部分で、磯山氏はリヒターの《ヨハネ受難曲》演奏を絶賛しています。 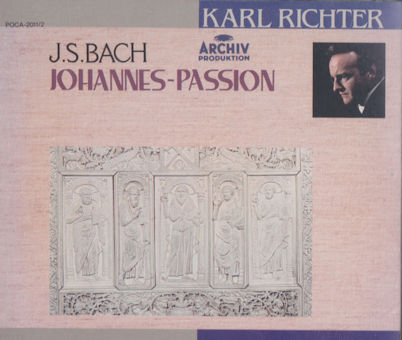 カール・リヒター「ヨハネ受難曲」CD(1964年 Archiv) 「カール・リヒターによるアルヒーフ・レーベルのバッハ四大宗教曲の録音は、1958年の《マタイ受難曲》によって開始され、1965年の《クリスマス・オラトリオ》によって、ひとまず終了した。これらはいずれも、バッハ演奏の歴史を書き換える、記念碑的な業績であった。4種の録音はまさにいずれ劣らぬ名演だが、その中で最高の演奏をあえてひとつ選ぶとすれば、この《ヨハネ受難曲》になるのではないだろうか」 さらに続けて、 「これほど高い緊張に貫かれた、血のしたたるほどに切実な《ヨハネ受難曲》を、私は、ほかに聴いたことがない。この不滅の録音は《マタイ受難曲》(1958年)とミザ曲ロ短調(1961年)の経験をふまえ、1964年に行われた。そしてリヒターは、以後二度と、《ヨハネ受難曲》を ― スタジオであれライヴであれ ― 残すことがなかった」 と結んでいます。 今回、『ヨハネ受難曲』を読み始めたときに上の解説を再読して、《ヨハネ受難曲》が磯山氏のライフワークとなっていく過程を思い浮かべました。 2.磯山 雅「ヨハネ受難曲」 しっかりした装丁の分厚い本の表紙帯には「名曲に秘められた謎を読み解く、バッハ研究の権威、渾身の遺作」と書かれています。「磯山バッハ論」の到達点というべきでしょう。 磯山氏のバッハ関連書には「バッハ=魂のエヴァンゲリスト」(1985年 東京書籍)と「マタイ受難曲」(1994年 東京書籍)があります。早い時期にこの二冊を入手した私は、これまで折に触れて参照し、自分の中のバッハ像を描いていました。今回、究極の「磯山バッハ」と言ってよい「ヨハネ受難曲」を手にすることが出来、前作「マタイ受難曲」以降、20年以上に亙る磯山氏のバッハ研究が更なる深みを湛えていることに感動しています。 巻末に添えられた補記(「終章に代えて」 伊東辰彦氏)によると、この本は2018年1月27日に不慮の事故に遭い、同年2月に逝去された故磯山 雅氏の遺稿に最小限の校訂を加えたものであるとのこと。磯山氏が以前からバッハの《ヨハネ受難曲》に関する著作を上梓したいという希望を持っており、並行して執筆していた博士論文「J.S.バッハの《ヨハネ受難曲》-その前提、環境、変遷とメッセージ」は、事故の前日の1月26日に提出先の国際基督教大学における口頭試問を経て受理されたそうです。学位論文とは別に一般読者向けに準備を進めていたのが本書の原稿で、磯山氏自身、前著の「マタイ受難曲」(1994年)に続く出版を強く望んでいたということです。 出版に手間取った理由として本人が記しているのは、 「《ヨハネ受難曲》は《マタイ受難曲》に先行する作品であるが、上演される度に手が加えられて、都合五つの稿によって伝えられている。そして背景が判然としないため、肝心のところで推測に頼らざるを得なかった」ということ。定年後も続けた探索の中で、ギリシャ語の習得を加えたのは、「《マタイ受難曲》執筆の時点でその能力がなく、福音書とその内容について、ルター訳を批判的に読むことができなかったことへの反省があった」 とのことです。 本の内容は 第1部 イエスの受難と「ヨハネ福音書」(第1~5章)P15-74 第2部 ヨハネ受難曲の歴史とバッハの上演諸稿(第1~4章)P75-144 第3部 バッハ《ヨハネ受難曲》全楽曲各論(第1~10章)P145-454 付:注、参考文献、補記:終章に代えて からなり、博士論文と並行して執筆されたことを裏付けるように、緻密で学術的な記述がなされています。  書出しの第1部では新約聖書の各福音書との比較の中で、ヨハネによる福音書の位置付けと記述の特徴、バッハのヨハネ受難曲に表れている音楽表現との関係が解説されています。 書出しの第1部では新約聖書の各福音書との比較の中で、ヨハネによる福音書の位置付けと記述の特徴、バッハのヨハネ受難曲に表れている音楽表現との関係が解説されています。第2部ではバッハの《ヨハネ受難曲》演奏記録を辿り、1724年の初演以来、1725年、1732年、1739年(未発表)1749年の5つの作曲稿があったとする中で、1749年の第4稿を元にした稿が現在演奏されていることを説明しています。 第3部は現在演奏されている《ヨハネ受難曲》全楽曲について、ドイツ語と日本語のテキストを掲げ、楽譜(パート譜含む)とともに詳述しているのが圧巻です。レコードの再生をしながら詳細を確認できるように作られています。参照する録音はできれば〝リヒター指揮〟でありたいと思います。 右の書影は磯山 雅著「ヨハネ受難曲」(2020年筑摩書房)です。 3.リヒターの《ヨハネ受難曲》を聴く リヒター指揮の《ヨハネ受難曲》を入手したのは前述のように20年以上前でしたが、その後に購入したBCJ(バッハ・コレギウム・ジャパン 指揮:鈴木雅明)や、ライプツィヒで求めてきた聖トーマス合唱団(指揮:G.クリストフ・ビラー)の録音もあり、このところ、リヒターの《ヨハネ受難曲》は脇に置かれていました。 今回、磯山氏の本を読み、解説を再読し、改めてリヒターの《ヨハネ受難曲》と向かい合うことになりました。ご紹介した第3部に詳述されている「全楽曲各論」を参照しながら演奏を味わうことに新鮮な楽しみを感じています。 冒頭に置かれた合唱曲 Herr, unser Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen Herrich ist! 主よ、われらの支配者よ、その栄誉、全地に栄えある方よ! から始まる10分を超える大合唱曲によって引き込まれるヨハネ福音書の受難記述の世界は他の福音書にない緊張感を伴っています。磯山氏がCDの解説で綴っているリヒター指揮への全幅の信頼を支えとして、曲の最奥部へ進んでみようと思います。 磯山氏の解説をもう一か所参照します。 「合唱は、あるときは興奮した群衆としてイエスを責め、その処刑を求める。またあるときは、コラールとして信徒共同体の立場から出来事に対応し、イエスを思いやり、悼み、また賛美する。群衆としての合唱がスリルにみなぎっているのは当然ともいえようが、リヒターは、コラールとしての合唱をさえ一定のトーンにとどめず、状況に応じて思い切った変化を、その表情に与えた。ここでは、コラールがドラマの一部として流れへと完全に組み込まれ、受難するイエスと、痛みを分かち合っている。そのほとばしるような気合は、われわれ聴く者をも強力に、ドラマへと巻き込んでしまう」 それに続けて、福音史家のソロを受持つエルンスト・ヘフリガー(テノール)、イエスのヘルマン・プライ(バス)、さらにアルトのヘルタ・テッパーを特筆して称賛しています。ヘフリガー、テッパーの二人は1958年版のリヒター指揮《マタイ受難曲》にも優れた歌唱が残されています。 先を急ぐようで憚られますが、終曲前(第39曲)の合唱 Ruht wohl, ihr heilligen Gebeine, die ich nun weiter nicht beweine, ruht wohl und bringt auch mich zur Ruh! 安らかに憩われませ、聖なるお身体よ、私は今後もう泣きますまい。安らかに憩われ、私をも憩いへと導かれますように。 続く終曲(第40曲)のコラール Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in Abrahams Schoss tragen, ああ主よ、あなたのいとしい天使に命じて、いまわの時を迎えた私の魂をアブラハムのふところへと運ばせてください。 それぞれの歌い出し部分を示しましたが、この二曲はとても美しく、第39曲で繰り返される Ruht wohl (ルート ヴォール:安らかに憩われよ)の旋律が何時までも耳に残ります。 イエスの捕縛からペテロの否認、ピラトの訊問を経て、十字架上の言葉、「成し遂げられた」まで、緊張感のある受難物語が展開されます。 おわりに 磯山雅先生がバッハ研究の成果として早い時期に上梓された二冊の大著から25年の歳月を隔てて「ヨハネ受難曲」を書きあげられた情熱に打たれます。 *磯山氏の著作は他にもありますが、本稿では触れておりません。 磯山先生とお会いした唯一の思い出は、1999年3月に二回、私の住む町の文化センターの教室で開催された「マタイ受難曲」の講義をお聴きしたことです。受講後に持参した前出の著書二冊を差し出して、サインをお願いしました。貴重な記念となりました。 磯山先生が1946年生れで私と同年であることを最近知りました。遺著の「ヨハネ受難曲」を手にできたことに「御縁」を感じています。 令和3年8月12日
稲林記 |