見たり聴いたり:
はじめに
アマチュアの合唱団として伝統のある千葉混声合唱団が創立65周年を迎え、記念演奏会でJ.S.Bachの「マタイ受難曲」を聴きました。会場は京葉銀行文化プラザ音楽ホールです。 「マタイ受難曲」は千葉混声合唱団(指揮:伊賀美 哲)の得意曲のひとつです。演奏会場ではソリストと合唱団の歌唱、舞台上部に字幕で表示された日本語訳と持参したドイツ語テキストを照合しながら聴きどころを確認していました。これを機会に、いまの自分にとっての「マタイ受難曲」の味わいを記してみることといたします。 バッハ「マタイ受難曲」の味わい 曲番は磯山雅「マタイ受難曲」(東京書籍)によります。 ① 第1曲 合唱とコラール「来たれ娘たちよ、ともに嘆け」 マタイ受難曲の壮大さと豊かな音楽性を象徴する冒頭曲が、聴衆をいきなり受難ドラマの世界に引き込んでしまいます。十字架を背負って坂道を歩かされているイエスの姿を二つのグループに分かれた合唱隊が対話的な歌唱で描く中、第三のグループが高い声でコラール(讃美歌:おお神の子羊、罪なくして)を歌い出します。オーケストラと組み合わさる重層的な音楽は単なる導入ではなく、受難劇のクライマックスを提示する効果があります。この入り方は大変ユニークで、初めて聴く人にとっても、「これがバッハだ!」と感じられるのではないかと思います。 ② 第10曲 コラール「私です、私こそ償わなくてはならないのです」 受難曲が始まって間もなく、いわゆる「最後の晩餐」の場面でイエスが告げた「あなたがたのうちの一人が私を裏切ろうとしている」という言葉に、弟子たちが驚いて「主よ、まさかわたしのことでは?」とざわめく場面で登場するコラールです。ヨハネ受難曲にも登場するこのコラールはルネサンス時代のオーストリアの作曲家、ハインリッヒ・イザークの世俗歌曲「インスブルックよさらば」の旋律が宗教詩に用いられて、コラールとして普及したと言われています。「インスブルックよさらば(Innsbruck, Ich muss dich lassen)」は私も以前から耳にしていますが、このコラールとの符合については磯山雅氏が著書「マタイ受難曲」(東京書籍)に書かれているのを読むまで気が付かずにいました。第二部の第37曲「誰があなたをこのように打ったのですか」も同じ旋律のコラールです。 ③ 第15曲 コラール「私を知ってください、私の守り手よ」 「最後の晩餐」が済んで一同がオリーブ山に出掛けた時に、イエスが弟子たちに向かい「今夜、お前たちは皆わたしにつまずく」と、自分が捕縛されたときにかれらが逃げてしまうことを予告します。それを受けた弟子たちの気持を表すコラールです。 「マタイ受難曲」全曲の中に調性を変えて5回登場する有名な「受難コラール」の最初の一つがこれです。この旋律に触れることで受難曲の気分がしだいに高まって行きます。 ちなみに、残りの4曲は次のとおりです。 第17曲 「私はここ、あなたのみもとにとどまろう」 ペトロの否認が予告された後 第44曲 「お前の道と、心の患いとを」 ピラトの尋問に対して無言のイエス、の後 第54曲 「おお、血と傷にまみれた御頭」 十字架の判決を受け群衆から侮辱される 第62曲 「いつしか私がこの世に別れを告げるとき」 イエスが息を引き取った直後 5つの「受難コラール」を改めて聴き比べてみると、旋律は同じですが調性の変化があり、それぞれの場面に応じた歌い方がなされています。劇的なピークは第54曲でしょうか。最後の第62曲は一番ゆっくりとしたテンポで歌われ、葬送の気分が漂います。 ④ 第20曲 アリア(テノール、合唱)「私はイエスのそばで目覚めていよう」 ユダの裏切りによる捕縛を予知したイエスがゲッセマネの園で神に祈る間、傍で座って目を覚ましているように言われていた弟子たちはみな眠ってしまいます。神に祈りをささげるイエスが3回戻ってみるたびに、眠りこけている弟子を見つけて哀しみます。この場面で歌われるテノールのアリア「私はイエスのそばで目覚めていよう」がオーボエの伴奏で軽やかな旋律を奏でます。歌の内容と現実が食い違うところが少しユーモラスです。 ⑤ 第29曲 コラール「おお人よ、お前の大いなる罪を嘆け」 ユダに導かれて祭司長や長老たちからつかわされた大勢の者がイエスを捕えて引っ立てて行きます。弟子たちはイエスの予告通りに、みな逃げてしまいます。ここで歌われる大きなコラールで第一部が終ります。この部分はバッハが「マタイ受難曲」を初演した1727年のときには別の短いコラールが置かれていたということです。現在演奏される「おお人よ、お前の大いなる罪を嘆け」は6分を超える大きなものです。 ⑥ 第38C曲 レチタティーボ 「そして外に出て、激しく泣いた」 イエスの捕縛で終る第一部に続いて第二部が始まります。祭司長や長老たちのところへ連行されるイエスを遠巻きについて行った弟子のペトロは群集から、「お前はガリラヤのイエスと一緒にいたね」、「この人はナザレのイエスと一緒でしたよ」、「確かに、お前もあの連中の仲間だ」と次々に言われて、恐ろしさのあまりその都度「何のことだかわからない!」、「そんな人は知らない」、「まったく知らない!」と三度否認すると、たちまち鶏が鳴くのを聴きます。ペトロはイエスが「鶏が鳴く前に、お前は三度私を知らないと言うだろう」と告げたのを思い出し、「そして外に出て、激しく泣いた」と語る福音史家の語り(レチタティーボ)が痛切です。「激しく泣いた」、ドイツ語で“ヴァイネテ ヴィターリッヒ”という言葉の哀切な表現に、「例え一緒に死のうとも、あなたを知らないとは言いません!」とイエスに誓ったペトロの悔恨があらわされます。 ⑦ 第39曲 アリア(アルト)「主よ、憐れみ給え」 上に記した「ペトロの否認」に続くアルトのアリアは、ペトロに代表される人間の弱さを痛切に表しています。曲のメロディーラインも深い哀しみを湛えて訴えかけてきます。そして次の短いコラール(第40曲「たとえあなたから離れても、私は再びみもとに帰ります」)につなげます。 ⑧ 第45a曲 レチタティーボ 「バラバ!」 祭司長カイアファの屋敷で行われた審問で長老たちは偽証者まで使った挙句、イエス自身に「神の子」と言わせることで、「死罪に値する」として、総督のポンテオ・ピラトに引き渡します。ここに至って、今更ながら自分の罪を悔いたユダはイエスを密告して得た銀貨30枚を祭司長らに返そうとしますが相手にされず、銀貨を神殿に放り投げて自殺します。 イエスに何の落ち度も認められない総督ピラトは、この時期(ユダヤの過越祭)に罪人一人を助命する風習があるのを思い出して「悪名高い囚人バラバと、このイエスとどちらかを釈放することができるが、どちらを選ぶのか」と群衆に尋ねます。このとき祭司長や長老たちに予め言い含められていた群衆は一斉に「バラバ!」と叫びます。たったひとこと合唱が声を揃えて「バラバ!」と叫ぶ場面は、マタイ受難曲の中でも強烈な印象を受けます。「では、キリストといわれているイエスはどうする?」と訊かれて、群衆は「十字架につけろ!」、「十字架につけろ!」と口々に叫び、イエスの処刑が決まってしまいます。 ⑨ 第57曲 アリア(バス) 「来たれ甘き十字架よ!」 十字架を背負わされて処刑の地、ゴルゴダの丘へ向かうイエス。シモンというキレネ人が途中からイエスに代わって十字架を担ぎます。ビオラ・ダ・ガンヴァの刻む歩みのテンポに合わせて歌われるバスのアリアが「来たれ甘き十字架よ!」です。“甘き十字架”と言う言葉はそぐわない感じを受けますが、十字架の苦しみを「甘い」と表現する宗教的な認識が第一部冒頭の合唱で描かれるゴルゴダへの歩みとともに、受難に向けた行進のクライマックスを形成します。 ⑩ 第61曲 レチタティーボ 「エリ、エリ、ラマ、アザプタニ?」 イエスが十字架に付けられた後、昼の十二時に全地が暗くなって、それが三時まで続きます。三時ごろ、イエスは大声で叫びます。「エリ、エリ、ラマ、アザプタニ?」。福音史家は、これを「わが神よ、わが神よ、なぜわたしをお見捨てになったのですか?」という意味であると語ります。受難曲の中で発する最後の言葉の後、イエスは息を引き取ります。「そして、息を引き取る」ドイツ語で“ウント フェアシート”という言葉を、福音史家は感情をこめて語ります。…イエスは死んだのです。 ⑪ 第64曲 レチタティーボ(バス) 「夕暮れに」 十字架から降ろされたイエスの遺骸は女たちに見守られ、アリマタヤ出身で金持ちのヨセフという弟子がピラトに願い出て、埋葬を許されます。バスで歌われるレチタティーボ「夕暮れに」、ドイツ語で“アム アーベント”はしっとりしたよい詩です 夕暮れの涼しいときに、アダムの罪は明らかになった 夕暮れに、救い主はそれを克服された 夕暮れに、ハトが再びやって来た。そしてオリーブの葉を一枚、口にくわえていた。 おお、美しい時よ!おお、夕暮れのひと時! 平和の約束が今、神となされた。 (後略) 日本語訳を示しましたが、ドイツ語の詩がとてもきれいなので、できればそのまま深く味わいたいです。 ⑫ 第65曲 アリア(バス)「おのれを清めよ、私の心よ」 これも埋葬の場面におけるアリアです。「おのれを清めよ、わが心よ」、ドイツ語で“マッヘ ディッヒ マイン ヘルツェ ライン”と歌いだすメロディーはとても清々しく、印象的です。はじめの部分が後にスペインのギタリスト、フランシスコ・タルレガによってギターの名曲「アルハンブラの想い出」に採り入れられたと聞いています。 ⑬ 第68曲 合唱「私たちは涙してひざまづき」 3時間を超えるバッハの「マタイ受難曲」を締めくくる最後の合唱が「私たちは涙してひざまずき」です。曲の中では「お休みください、安らかに」、ドイツ語で“ルーヘ ザンフテ”という言葉が繰り返されて、受難曲は終わります。 おわりに 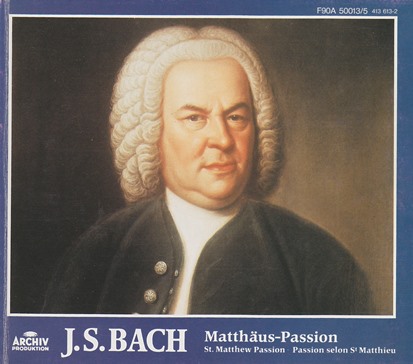 バッハの「マタイ受難曲」を聴いたのは40歳代の前半です。最初に入手したレコードはカールリヒターのミュンヘンバッハ合唱団とオーケストラによるLPでした。その後CDになって発売されたカールリヒターの2つの録音をはじめ、さまざまな演奏を聴いてきましたが、言葉の壁もあり、テキストに踏み込んだ鑑賞、理解は長い間できませんでした。 バッハの「マタイ受難曲」を聴いたのは40歳代の前半です。最初に入手したレコードはカールリヒターのミュンヘンバッハ合唱団とオーケストラによるLPでした。その後CDになって発売されたカールリヒターの2つの録音をはじめ、さまざまな演奏を聴いてきましたが、言葉の壁もあり、テキストに踏み込んだ鑑賞、理解は長い間できませんでした。その後もバッハのカンタータやモテット、ミサ曲、オラトリオなどを聴き続け、ドイツ語の断片が少し耳に残るようになってから「マタイ受難曲」を聴くと、言葉の雰囲気を少し感じることができるように思われてきました。20年前に入手した磯山雅氏の「マタイ受難曲」(1994年、東京書籍)を取り出して、手元にあるいくつかのCDのブックレットやネット上で公開されている歌詞対訳(例:「音楽の森 バッハ」)を参照しながら、今回自分の中で特に印象の強い歌唱を抜き出してみました。 「マタイ受難曲」の歌唱は全曲すべて素晴らしく、どこから聴いても「マタイだ!」と思えるほどですが、自分が特に注目して聴いていた部分を抽出してみました。 *右上の写真はカールリヒター指揮の1979年録音CD(ARCHIV版)のブックレット表紙です。
最後に大変重要なことなのですが、敬虔なキリスト教徒ではない一般の日本人のひとりとして、キリスト受難曲の本来の意味が理解できてないのではないかという懸念があります。これに対して、上記の磯山先生がある所で「私はバッハをいま教会に閉じ込めようとか、信仰仲間のものにしようとかいうのには全く意味がないと思う。ただ「マタイ受難曲」を聴いて感動している心というのはやはり、一種宗教的な心であると思います。」と語っておられたのを当面の答えとして、更にマタイ体験を続けていきたいと思います。 以上
平成28年9月4日 稲林記
|