���ꂱ��l����F
�@10�N�O���瑱���Ă���h�C�c�ւ̗��̖ړI�̈�͑�o�b�n�iJ.S.Bach)�̑��ՒT�K�ł��B�ŏI�C�n�̃��C�v�c�B�q���N�_�ɂ��āA���a�n�A�C�[�i�n�A���y�ƂƂ��Ċ����������C�}�[���A�P�[�e�����͂��߂Ƃ��钬�X�����ɏ����Ă������ŁA����͓�S�N�قǑk��܂����A�����͈͂̏d�Ȃ�}���e�B���E���^�[�ɂ����Ώo��܂����B�o�b�n�̐��܂ꂽ�A�C�[�i�n�̍L��ɂ͂��̒n�Ń��e����w�Z�ɒʂ������^�[�̓���������A�X�̔w��ɂ��т��郔�@���g�u���N��ł͏@�����v�Ń��[�}���c����j�傳�ꂽ���^�[���ی삳���1�N�߂��B��Z�݁A�����̃h�C�c��|����s���Ă����u���^�[�̕����v���ۑ�����Ă���̂����邱�Ƃ��ł��܂����B �@�A�C�[�i�n���班���k�ɂ���~���[���n�E�[���͎Ⴋ���̃o�b�n������̃I���K�j�X�g�Ƃ���1�N�Ԃ��߂������X�ł��B�����Ńg�[�}�X�E�~�����c�@�[�ɏo��܂����B�ŏ���2013�N5���A�����č��N��6������x�ڂƂȂ�܂����B   �A�C�[�i�n�̃J�[���L��ɂ��郋�^�[���@�@�@�Ɓ@�@�@���@���g�u���N����́u���^�[�̕����v �P�D�~�����c�@�[�Əo�  �@�~���[���n�E�[���̓h�C�c�̒������A�e���[�����Q���B�ɂ���Â��X�ŁA��������鍑���R�s�s�Ƃ��Ĕ��W���܂����B���̊X��16���I���߂̏@�����v�̎����ɔ��������h�C�c�_���푈�̋��_�̈�ł���A�_����J���҂��w�������̂��g�[�}�X�E�~�����c�@�[�Ƃ����_�w�҂ł��������Ƃ�m�����͍̂ŏ��̖K��̂Ƃ��ł����B�~���[���n�E�[���ւ̓A�C�[�i�n����S���𗘗p����ƁA�S�[�^�ŏ抷���ĕГ�50���قǂōs�����Ƃ��o���܂��B�Ⴋ�o�b�n����E�����u���u���W�E�X����v��ڎw���āA�n�}�����Ȃ�������n�߂�ƊԂ��Ȃ����̉E���ɌÂ�����������A�ǂɁu�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�w�Z�v�ƕ\������Ă��܂����B���ɖʂ����O��ɋ����i�E��̎ʐ^�j���u����Ă���̂��������̂��A�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�Ƃ̏o��ł��B �@�~���[���n�E�[���̓h�C�c�̒������A�e���[�����Q���B�ɂ���Â��X�ŁA��������鍑���R�s�s�Ƃ��Ĕ��W���܂����B���̊X��16���I���߂̏@�����v�̎����ɔ��������h�C�c�_���푈�̋��_�̈�ł���A�_����J���҂��w�������̂��g�[�}�X�E�~�����c�@�[�Ƃ����_�w�҂ł��������Ƃ�m�����͍̂ŏ��̖K��̂Ƃ��ł����B�~���[���n�E�[���ւ̓A�C�[�i�n����S���𗘗p����ƁA�S�[�^�ŏ抷���ĕГ�50���قǂōs�����Ƃ��o���܂��B�Ⴋ�o�b�n����E�����u���u���W�E�X����v��ڎw���āA�n�}�����Ȃ�������n�߂�ƊԂ��Ȃ����̉E���ɌÂ�����������A�ǂɁu�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�w�Z�v�ƕ\������Ă��܂����B���ɖʂ����O��ɋ����i�E��̎ʐ^�j���u����Ă���̂��������̂��A�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�Ƃ̏o��ł��B�@���s�X�̓����ɋ߂����u���W�E�X����ŁA��X�����o�b�n���ɉ�A��q���ɂ��Q������Ă���A�X������ċ��s���ɂ֓���ƁA�K�C�h���������n�߂��Ƃ���ł��B�U����܂܁A�n�܂�������ɃK�C�h�c�A�[�ɎQ�����܂����B���Ă̒鍑���R�s�s�~���[���n�E�[���̈�\���Љ��A�_���푈�ւ̌��肪�Ȃ��ꂽ��c���������Ă��炢�܂����B����}���������v�w�͓r���ł���������ĊO�ɏo�āA�߂��̃r�A�E���X�g�����Œ��H�����A�X���͂ޏ�ǂ̏������Ă���ăA�C�[�i�n�ɖ߂�܂����B���̂Ƃ��A���X�g�����̑O�ɂ������������u�_���푈�L�O�فv�ł����B�K�C�h����ɕt���čs���Θb���������̂ł��傤���A���̂��ƂɋC���t�����͓̂��{�ɋA���Ă���ł��B�X�̎勳��ł��鐹�}���G������̔��X�ɒu����Ă����u�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�v�̃p���t���b�g����肵�Ă����̂��A�B��̎肪����ƂȂ�܂����B�h�C�c��ŏ����ꂽ16�ł̏����q�͕���Ɂu�@�����v�̃A�E�g�T�C�_�[�v�Ə�����Ă���̂������C�ɂȂ�܂������A�ƂɎ����A���Ă�����e���\���m�F���邱�Ƃ��Ȃ��A���̎����ƂƂ��Ɏd��������ł��܂����B  �@���N�̃h�C�c�ւ̗���5�N�Ԃ�ɓ����̃��C�v�c�B�q�A�h���X�f���܂ōs���A�t�����N�t���g�ɖ߂�Ȃ���A���C�}�[���A�G�A�t���g�A�A�C�[�i�n���ĖK���܂����B����̓A�C�[�i�n����o�X�ł܂������ɖk�サ�ăe���[�����Q���̐X�������ă~���[���n�E�[���̋��s�X�ɓ���܂����B�o�X�̏��v���Ԃ�1���Ԃقǂł��B���̓��͌��j���Ŏ�v�ȋ����{�݂����J����Ă��Ȃ����Ƃ��ē����Œm�炳��܂������A���s���ɂ����͈ȑO�Ɠ����悤�Ɍ��w�ł��܂����B�����̕lj�ɕ`����Ă���u�_���푈�v���w������g�[�}�X�E�~�����c�@�[�̎p�i����̎ʐ^�j�ɋC���t���A�v���o�����̂��u�_���푈�L�O�فv�ł����A�c�O�Ȃ��炻�����x�ق̂悤�ł��B�X������Ă��������x�ē����ɗ�������ċL�O�̕i�F���钆�Ɂu�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�F���̐��U�ƋƐсv�Ƃ����^�C�g���̏��^�{�������܂����B���\���ɏ����ꂽ�����̒��Ɂu�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�F���^�[�Ɍ���ꂽ���ԁv�Ƃ������₩�łȂ����t������܂��B���̌��t�ɖ�����Ė{����肵�܂����B �@���N�̃h�C�c�ւ̗���5�N�Ԃ�ɓ����̃��C�v�c�B�q�A�h���X�f���܂ōs���A�t�����N�t���g�ɖ߂�Ȃ���A���C�}�[���A�G�A�t���g�A�A�C�[�i�n���ĖK���܂����B����̓A�C�[�i�n����o�X�ł܂������ɖk�サ�ăe���[�����Q���̐X�������ă~���[���n�E�[���̋��s�X�ɓ���܂����B�o�X�̏��v���Ԃ�1���Ԃقǂł��B���̓��͌��j���Ŏ�v�ȋ����{�݂����J����Ă��Ȃ����Ƃ��ē����Œm�炳��܂������A���s���ɂ����͈ȑO�Ɠ����悤�Ɍ��w�ł��܂����B�����̕lj�ɕ`����Ă���u�_���푈�v���w������g�[�}�X�E�~�����c�@�[�̎p�i����̎ʐ^�j�ɋC���t���A�v���o�����̂��u�_���푈�L�O�فv�ł����A�c�O�Ȃ��炻�����x�ق̂悤�ł��B�X������Ă��������x�ē����ɗ�������ċL�O�̕i�F���钆�Ɂu�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�F���̐��U�ƋƐсv�Ƃ����^�C�g���̏��^�{�������܂����B���\���ɏ����ꂽ�����̒��Ɂu�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�F���^�[�Ɍ���ꂽ���ԁv�Ƃ������₩�łȂ����t������܂��B���̌��t�ɖ�����Ė{����肵�܂����B �@5�N�O�̃p���t���b�g�ɏ�����Ă����u�@�����v�̃A�E�g�T�C�_�[�v�ɉ����āA������肵���{�́u���^�[�Ɍ���ꂽ���ԁv�Ƃ������t�����������ŁA�����Ă����~�����c�@�[�ւ̊S���ĂыN������܂����B����ɂ��Ă��u�_���푈�L�O�فv�i�E�̎ʐ^�j�̋x�ٓ��ɓ����������Ƃ͐ɂ��܂�܂��B �@5�N�O�̃p���t���b�g�ɏ�����Ă����u�@�����v�̃A�E�g�T�C�_�[�v�ɉ����āA������肵���{�́u���^�[�Ɍ���ꂽ���ԁv�Ƃ������t�����������ŁA�����Ă����~�����c�@�[�ւ̊S���ĂыN������܂����B����ɂ��Ă��u�_���푈�L�O�فv�i�E�̎ʐ^�j�̋x�ٓ��ɓ����������Ƃ͐ɂ��܂�܂��B�@���N�̗��ł̓G�A�t���g�Ń��^�[���C�Ƃ����A�E�O�X�e�B�[�i�C���@�ɗ������A���^�[�Ɋւ���{�����肵�Ă��܂����̂ŁA���^�[�̑��ՂƏƍ����Ȃ���~�����c�@�[�ɂ��Ē��n�߂܂����B���t�̕ǂ�����A�h�C�c��̖{�⎑�������ł͗����ł��Ȃ�����������܂��̂ŁA�莝���̖{��A����ɓ��肵�������̖{�i�a����܂ށj�߂���X�̒�����A���ڂ낰�Ȃ��猩���Ă������Ƃ��������߂Ă��������Ǝv���܂��B �Q�D���^�[�̏@�����v �@���{�l�̎����������ʂɒm���Ă���̂�1517�N�i��N��500�N�j�Ƀ}���e�B���E���^�[�����B�b�e���x���N�Łu��܉ӏ��̒��v���s���A�@�����v�̌�����ꂽ�Ƃ������Ƃł��B���̓��e�ɂ͓����A���c���̉��ɍs���Ă����u�ƍߕ��v�̔̔���ᔻ���邱�Ƃ��܂܂�Ă����ƋL�����Ă��܂����A��܉ӏ��̋�̓I�ȓ��e�͂���܂Ŗڂɂ��Ă��܂���ł����B���̂��Ƃ��܂߂ă��^�[�̏@�����v�ɂ��Ē��ׂĂ݂܂����B 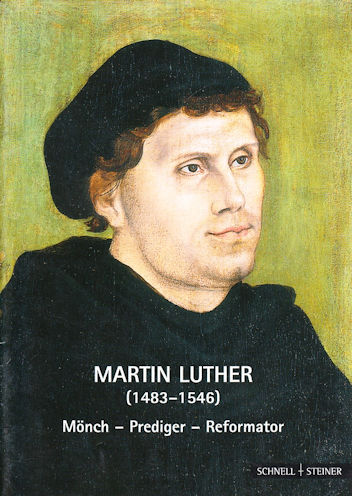 �@���^�[���@�����v�̒ɂ������ċL�q���������̈ꕔ�͓��{�����o�ł���Ă��܂��i�u�@�����v�O�啶���v�[��q�N��@�u�k�Њw�p���Ɂj�B�{�̖`�����u��܉ӏ��̒��v�i1517�N�j������A�������1520�N�ɏo�ł��ꂽ�O�̕����A�u�L���X�g���̉��P�ɂ��āv�A�u����̃o�r�����ߎ��ɂ��āv�A�u�L���X�g�҂̎��R�ɂ��āv�̘a���^����Ă��܂��B�L���X�g���̕��O�҂ɂ͂Ȃ��݂̔����p��i��F�T�N�������g�A�������߁A�ܗG�F���傭�䂤�j������A���i�K�ł͓ǂݗ����Ȃ��畵�͋C�𖡂키���x���ɂƂǂ܂��Ă��܂��B���͈̔͂ł͂���܂����A���^�[�̕��e�A���v�ւ̎p���Ɨ����ʒu�A�l�Ԗ����_�Ԍ��邱�Ƃ��o���܂��B �@���^�[���@�����v�̒ɂ������ċL�q���������̈ꕔ�͓��{�����o�ł���Ă��܂��i�u�@�����v�O�啶���v�[��q�N��@�u�k�Њw�p���Ɂj�B�{�̖`�����u��܉ӏ��̒��v�i1517�N�j������A�������1520�N�ɏo�ł��ꂽ�O�̕����A�u�L���X�g���̉��P�ɂ��āv�A�u����̃o�r�����ߎ��ɂ��āv�A�u�L���X�g�҂̎��R�ɂ��āv�̘a���^����Ă��܂��B�L���X�g���̕��O�҂ɂ͂Ȃ��݂̔����p��i��F�T�N�������g�A�������߁A�ܗG�F���傭�䂤�j������A���i�K�ł͓ǂݗ����Ȃ��畵�͋C�𖡂키���x���ɂƂǂ܂��Ă��܂��B���͈̔͂ł͂���܂����A���^�[�̕��e�A���v�ւ̎p���Ɨ����ʒu�A�l�Ԗ����_�Ԍ��邱�Ƃ��o���܂��B�@���^�[��1483�N�ɃG�A�t���g�����k�̃A�C�X���[�x���Ő��܂�A�߂��̃}���X�t�F���g�Ŋw�сA�A�C�[�i�n�̃��e����w�Z�ɒʂ�����A1501�N��18�ŃG�A�t���g��w�ɓ��w���܂����B22�Ŗ@�w���ɐi�݂܂����A�u�����v�����̂��@�ɃA�E�O�X�e�B�[�i�C���@�ɓ����Ďi�ՂƂȂ�A�_�w�������n�߂܂����B���̌�A29�Ő_�w���m�A���B�b�e���u���O��w�̐��������ɂȂ�܂��B���̂���u���̑̌��v�ƌĂ��M�ւ̊J��̌�������܂����B�u�����v�Ɓu���̑̌��v�͂�������_�鐫�̂���C�t���̑̌��ł��B�u�����v�ŐM�������u���A�u���̑̌��v�Łu�M�`�F�v�ɖڊo�߂��ƌ����Ă��܂��B �@1515�N�Ƀ��[�}���c���I�\�����h�C�c�����ł��ܗG��i������u�ƍߕ��v�j�̔������������Ƃɑ��āA1517�N10���Ƀ��^�[�́u��܉ӏ��̒��v�����B�b�e���x���N�鋳��̔��Ɍf�����A�@�����v�ւ̒[�����J���܂��B���̂Ƃ����^�[��34�ł����B���^�[�̖���N�ɑ��铢�_�i�n�C�f���x���N�A���C�v�c�B�q�j��ْ[�R��i�A�E�O�X�u���N�j�����X�ɍs���钆�ŁA�܂Ƃ߂�ꂽ�������O�f�́u�O�啶���v�ł��B������15���I���ɃO�[�e���x���N�ɂ�蔭�����ꂽ���ň���Z�p�ɂ���ďo�ł���A�����̐l�ɒm���邱�ƂƂȂ�܂����B �@1521�N�Ƀ��[�}���c���琳���ɔj�傳�ꂽ���^�[�́A1�N�߂����@���g�u���N��ɕی삳�ꂽ�ピ�B�b�e���x���N�ɖ߂�A�V���̃h�C�c�����o�ł���ƂƂ��ɉ��v�^�����p�����܂��B���̌�A1524�N�Ƀh�C�c�̔_���푈���N����܂����B�_���푈�ɑ��郋�^�[�̑Ή��ɂ��Ă͌�قǂ��b���܂��B �@���^�[��1525�N�A42�̂Ƃ��ɏC�����ł����������ƌ������ĉƒ�������܂����B�������������̕������o�ł��A1534�N�ɂ͋����̃h�C�c�������������A���v�̐��i�ɓw�߂Ă��܂��B���^�[�̒�N�����@�����v�̗���̒��ŁA�����̐l���������A���ꂼ��̎咣�A�A�g�E�Η��̎p������܂����B�~�����c�@�[�Ƃ̊W�����̒��̂ЂƂƍl���Ă悢�悤�ł��B���^�[�̎咣�̍��q�́u�M�`�F�v�ƌĂ��_�̉����ւ̊��ӂɊ�Â��M�ł����B�@�����v�̓����A���^�[���ًc���������̂͐l�Ԃ̜��ӓI�ȉ��߂����������ɂ�鋳�c�_�Ƃ��鋳��g�D�̈�E�ɑ��Ăł���A�����I�Ȍ��͂ł���c��⏔��ւ̓G�ΐS�͊ł������悤�Ɍ����܂��B���̂�����̃j���A���X�����ɂ��b����_���푈�ւ̑Ή��̒��Ŗ��炩�ɂȂ�܂��B �R�D�~�����c�@�[�Ɣ_���푈 �@�g�[�}�X�E�~�����c�@�[��1489�N���Ƀh�C�c�����̃V���g���x���N�Ő��܂�܂����B���^�[���V�N���ł��B1506�N�Ƀ��C�v�c�B�q�ŏA�w���A1512�N�ɂ̓I�[�f���͔Ȃ̃t�����N�t���g�i�t�����N�t���g�E�A���E�}�C���Ƃ͕ʂ̒��j�ő�w�ɓ��w���Ă��܂��B1513�N�ɂ̓A�b�V�F�����x���ƃn���̏@���w�̑㗝�����ƂȂ�A���̍��n���o�[�V���^�b�g�̎i����i�ՂƂȂ��āA1516�N�ɂ͏C���@���㗝�ƂȂ�܂����B1517�N�A18�N�ɂ̓��^�[���@�����v���n�߂����B�b�e���x���N�ɑ؍݂��A1519�N�ɂ̓��^�[�̒Ɋւ��čs��ꂽ���C�v�c�B�q�_���ɂ���������Ă��܂��B��1520�N�Ƀ��^�[�̐��E�Ń��C�v�c�B�q�̓�ɂ���c���B�b�J�E�̒��̐����t�ɏA�C���܂����B �@�c���B�b�J�E�ɂ͎�v�ȏ��ƘH���������Ă��āA��������Ɍo�ϓI�Ȕ��W�𐋂��Ă��܂����B�~�����c�@�[�͒��C���X�ɁA�����̃t�����`�F�X�R�C����m�Ƃ̊Ԃő������N�����Ă��܂��B�~�����c�@�[�̍s�Ȃ����ŏ��̐����ŋ��`�̈قȂ�C������������낵�����Ƃ������ł������悤�ł��B�c���B�b�J�E�Ń~�����c�@�[�͕n�����E�l�̐e���ƒm�荇���A�Љ�ɑ���s��������J���ґw�ɋ߂Â��Đ[���S���܂����B���̂��߂��A�A�C��P����̃��^�[���̎莆�Ń��B�b�e���x���N�ɂ����郋�^�[�̉��v�Ƃ͕����̈قȂ銈���ւ̎u�𖾂炩�ɂ��Ă��܂��B �@���N��1521�N�Ƀ~�����c�@�[�̓t�����`�F�X�R�C����⒬�̊����Ƃ̏Փ˂��瓦��ă`�F�R�̃v���n�Ɉڂ�܂��B�v���n���܂ރ{�w�~�A�n����100�N�O�Ƀ����E�t�X���ْ[�҂Ƃ��ĉΌY�ɂ��ꂽ��A���[�}����Ƃ͋�����u���Ă����n��ł��B���̔N��6������11���܂Ńv���n�ɑ؍݂����~�����c�@�[�́A�u�V�����g�k�I����v�̌��݂��Ăъ|����u�v���n�錾�v�\���܂����B���ꂪ�ނ̍ŏ��̐_�w�I�ӌ��\���Ƃ���Ă��܂��B �@�v���n����ɂ����~�����c�@�[��1523�N��3���ɐ��܂�̋��̃V���g���x���N�ɋ߂��A���V���e�b�g�̐����n�l����q�t�ɔC������Ē��C���܂����B�~�����c�@�[�̓A���V���e�b�g�Ő����̒�����Ȃ��A�Ǝ��̋�����`�����Ėq�t�Ƃ��Ă̊������n�߂܂��B�A���V���e�b�g�̎s���Ǝs�Q����͔ނ����}���A�ߍx�̍z�R�J���҂����������߂ɏW�܂��Ă��܂������A���̒n��̗̎�ł���}���X�t�F���g�̃G���l�X�g���i�J�g���b�N�j�͂���������A�₪�čz�R�J���҂��~�����c�@�[�̐��������Ƃ��֎~�����̂ŁA��������~�����c�@�[�ƌ������Η����A�G���l�X�g���͔ނ�ߕ߂��悤�Ƃ��܂����B�~�����c�@�[�ɂ��J���ґw�̑g�D���Ɨ̎�Ƃ̑Η��͑����A����1524�N8�����߂ɔނ̓A���V���e�b�g��čs���܂����B �@�~�����c�@�[���~���[���n�E�[���ɂ���ė����̂�1524�N8�����{�ł����B�����葁���A�O�N2���ɂ��̒��ōŏ��Ƀ��^�[�̋�����������̂́A�~���[���n�E�[���o�g�̌��C���m�n�C�����b�q�E�v�@�C�t�@�[�ł����B�܂������ԂɎx���҂������A�n�����l�X�𖡕��ɕt�����v���ɑ��Ďs�Q����͌����I�ɗ��������̂ł����A���̌㊈�����G�X�J���[�g���ė��D���N���������߁A8���Ƀv�@�C�t�@�[�͒�������Ȃ��Ă͂Ȃ�܂���ł����B���̃v�@�C�t�@�[��1�N��ɖ߂��ė���̂ƑO�サ�ă~�����c�@�[�����̒��ɓ���܂����B �@�ނ��������咣�͒��O�Ɉ���E�o�ł��ꂽ�u�s�^���Ȃ��̐��̌�����M�����J�������ɂ���Ēf�łƂ��Ė\�I����c�v��A����ɑ����Ď��M���ꂽ���^�[�ւ̔ᔻ�����ł���A���Ȃ�ߌ��Ȃ��̂ł��B���̎����Ƀ~���[���n�E�[���ł�1�N�O�Ƀv�@�C�t�@�[���N�������\���ȗ��̓��ڂ̖��O�I�N���N����A�s�������S���A�Q������ϊv��]�V�Ȃ�����܂��B�~�����c�@�[�ƃv�@�C�t�@�[�͐V���Ȏs�̍j�̂����u�_�̉i���̌_��c�́v�Ƃ������̌R���g�D���������Ďs�̎��������낤�Ƃ��܂������A�ߍx�̕ێ�I�Ȕ_���̎x�����s�Q����ɂ���ĂX�����ɒǕ�����Ă��܂��܂��B �@���̌�A�v�@�C�t�@�[�͂��̔N�P�Q���ɒ��ɖ߂�A�~�����c�@�[�����N�Q�����ɍĂу~���[���n�E�[���ɋA���ė��āA���̊ԂɎ����������Ă������O�g�D�̏�ɗ����āA�����e�n�Ŕ������Ă����_���I�N�ƌĉ����ė̎��c��ɑ��钼�ړI�Ȑ킢�ɓ˂��i�݂܂��B����ɂ��~���[���n�E�[�����h�C�c�_���푈�̋��_�̈�ƂȂ�܂��B �@�@�@�����v������ɂ��āA�_������������Ń��[�}������łȂ������̌��͂ł���c��E�̎��ɂ����킢�������N�������Ƃ̓��^�[�̋��e����Ƃ���ł͂���܂���B������h�C�c�ŋN�������_���̖I�N�ɑ��Ă͗����������A�c��E�̎�ւ̂Ƃ�Ȃ����s�������^�[�ł����A�����Ɏ����Ă͏@�����v�̎�|�Ɨ��ꂽ�Љ�I�ȑ����ł��邱�Ƃ���A�_���R�ւ̔ᔻ�ƂƂ��ɍc��E�̎�ւ̒����v�����s���܂��B����Ɉӂ����������̎叔���𗦂��Ē����Ɍ������܂��B  �@�~�����c�@�[�̓~���[���n�E�[���̓��A�t�����P���n�E�[���ɏI������6000�l�]��̔_���R�ɍ������A�A���V���e�b�g���牞���ɋ삯�t�������Ă̒��Ԃ����킹�ď���R���}�������܂����B5��10���Ƀt�����P���n�E�[���ɒ������~�����c�@�[�́A5��14���ɗ̎�R�Ƃ̍ŏ��̐킢�����܂������A��15���ɂ͔_���R�͉�œI�ɔs�k���A�ꎞ�g���B�����~�����c�@�[���Ԃ��Ȃ��������ĕߔ�����Ă��܂��܂��B�߂���ꂽ�~�����c�@�[�͋߂��̃w���h�����Q����ɍS������āA�q�⍉�������A�ʂ̏ꏊ�ŕ߂��ꂽ�v�@�C�t�@�[���ƂƂ��ɁA5��27���Ƀ~���[���n�E�[���̍x�O�ŏ��Y����܂����B���̎��~�����c�@�[��35�ł����B �@�~�����c�@�[�̓~���[���n�E�[���̓��A�t�����P���n�E�[���ɏI������6000�l�]��̔_���R�ɍ������A�A���V���e�b�g���牞���ɋ삯�t�������Ă̒��Ԃ����킹�ď���R���}�������܂����B5��10���Ƀt�����P���n�E�[���ɒ������~�����c�@�[�́A5��14���ɗ̎�R�Ƃ̍ŏ��̐킢�����܂������A��15���ɂ͔_���R�͉�œI�ɔs�k���A�ꎞ�g���B�����~�����c�@�[���Ԃ��Ȃ��������ĕߔ�����Ă��܂��܂��B�߂���ꂽ�~�����c�@�[�͋߂��̃w���h�����Q����ɍS������āA�q�⍉�������A�ʂ̏ꏊ�ŕ߂��ꂽ�v�@�C�t�@�[���ƂƂ��ɁA5��27���Ƀ~���[���n�E�[���̍x�O�ŏ��Y����܂����B���̎��~�����c�@�[��35�ł����B�@��̌����҂ɂ��h�C�c�ɂ�����_���푈�̊��Ԃ�1524�N5��26�����瓯26�N7��2���܂łƂ���Ă��܂��B�~�����c�@�[���~���[���n�E�[����Ǖ�����Ă���1524�N�̏��Ă���25�N2�����܂ł���i�K�Ƃ������͓�h�C�c�����S�ł����B25�N3���͂��߂��璆�E��E�����h�C�c�̊e�n�ňꝄ���N����A���A�E�l�A�C���@���̗��D�A�j�Ȃ���܂����B25�N4���㔼�ɂ͈Ꝅ�̐������n�܂�A�암�V�����@�[�x���̔_�����̎傽���̘A���R�ɔs��A5�����ɂ̓��F���e���x���N�A�G���U�X�A�e���[�����Q���̔_���������s�k�𐋂��A6�����߂Ƀt�����P���������ɂȂ�A����ɂ���Ĕ_���푈�͏I�����܂��B�_���푈���\������X�̈Ꝅ�́A���ꂼ��Ǝ��̎w���ҁA�v���A�����̌o�܂������Ă��āA���̒��S���@���I�v���ɂ������Ƃ͌����܂���B���̒��ɂ����āA�~�����c�@�[�̎w���ɂ��킢�ł́A�ޓƓ��̐������߂Ƌ��`�̎咣�Ɋ�Â��ϊv�v��������܂��̂ŁA�@�����v�Ƃ̊֘A�ɂ����Ē��߂�K�v�����肻���ł��B �S�D���^�[�ƃ~�����c�A�[ �@�_���푈�S�̂̒��S���@���I�v���ɂ������Ƃ͌����Ȃ����Ƃ��m�F���܂������A�~���[���n�E�[�������_�Ƃ���_���R�ɑ���~�����c�@�[�̎w�����@���I�ȖړI�ƌ��т��Ă������Ƃ͔ގ��g�̌��t�ɂ���Ă����炩�ł��B �@�~�����c�@�[�����^�[�̐��E�ɂ���ăc���B�b�J�E�̒������t�Ƃ��Ă���ė��������́A���B�b�e���x���N�̃��^�[�E�O���[�v�Ƃ݂Ȃ���Ă����悤�ł��B�������A�~�����c�@�[�ɂ͔ޓƎ��̃L���X�g����e������A�������߂ɂ����Ă����ɐ_���`�ƌ�����슴�I�Ȗʂ����������悤�ł��B����̃��^�[���ގ��g�̐��������Ɛ_�w�I�ȒT���Ɋ�Â��F���Ƌ���g�D�ւ̔ᔻ�Ɋ�Â��ď@�����v�̉ߒ���i��ł��܂��B �@�ȉ��̎O�_�͊T���I�Ȉ�ۂł����A��l�̊Ԃɖ��m�ȈႢ�������܂��B �@�@�M�̊�Ձ@ �@���^�[�������ɏ�����Ă���L���X�g�̌��t���B��̐M�ւ̎肪����ł���Ƃ����̂ɑ��āA�~�����c�@�[�͐����ƕ���ŗ��@�ƌĂ��L���X�g���k�̍s���K�͂ɂ܂Ŋg�����Ƃ����M�̊�ՂƂ��Ă��܂����B �@�A���[�}����Ɛ������͂ւ̑Ή� �@���^�[�̓��[�}���c�Ƃ��̎x���g�D���i�߂Ă���l�X�Ȏ{��ƃL���X�g���̋��`���߂Ɋւ��Ĉًc�������L���X�g����̉��v��������ŁA�c���̎傽���̐����I�ȓ����ɂ��Ă͐l�ԎЉ�̂��ƂƂ��Đ[���������邱�ƂȂ��A�T���߂ɑΉ����Ă��܂��B �@�~�����c�@�[�̓��[�}����Ɛ������͂��܂߂��@���I�A�Љ�I�ȓ����@�\�ɑ����肷�ׂĂ�_����̌[���ɂ����̂Ƃ��Ċv���I�ɕϊv���邱�Ƃ��߂����܂����B �@�B���v�̕��@�ƕ��j �@���^�[�͏@�����v�����́u��܉ӏ��̒��v�Ŏ����̈ӌ�����āA�W�҂ɂ�铢�_���Ăъ|���Ă���A���̌�̐i�W�̒��ł������ɂ��𒆐S�ɐ����Ă��܂��B �@�~�����c�@�[�͎Љ�I�Ȗ������̂��߂̕ϊv��_�̖��ɂ����Đ��s���邱�Ƃ����Ă���A�������͂Ƃ̕��͓�������i�Ƃ��đI�т܂����B �@��l�̊Ԃ̊�{�I�ȍ��ق͑������疾�炩�ɂȂ��Ă��܂��B���^�[�̐��E���ăc���B�b�J�E�̐����҂Ƃ��ĕ��C�����~�����c�@�[���A�A�C2�P����ɂ͎Љ�I�ȕs���w�Ɛڋ߂��āA���^�[�̐i�߂���v��ᔻ���Ă��܂��B�c�E�B�b�J�E��v���n�A�A���V���e�b�g�ƍs����X�Ŗ��������N�����~�����c�@�[�ɒ��ڂ܂��͊W�҂ւ̏��Ȃɂ�胋�^�[���ӌ����q�ׂĂ��܂��B�u�͂ɂ�鑭���ւ̔��R�A�g�̓I�����̓T�^�����������������Ă���̂��B���L���X�g�͎�������Ȃ��Ă��łт�͂����B�_�̌��t�Ɏd����҂́A�r�Â��Ő���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�i�I���t���[�h���b�q������ւ̃��^�[�̎莆�F1524�N6���j�@�~�����c�@�[�̓��^�[�ւ̓G�ӂ��B�����u�\�����R�̂���ٖ��A����������Ȃ܂ʂ邢�����𑗂郔�B�b�e���x���N�̓��̐l�i���^�[�j�ւ̉v�i1524�N12���o�Łj�Ƃ���������˂��t���Ă��܂��B �@���^�[���_���푈�̒��É�������ɋ��߂��u�_���̎E�l�E�����c�ɍR���āv�̕����͏���Ɂu���n�t���v��^���āA�_���푈�������܂��ɏI�������܂����B�u�͂ɂ�炸�A���Ƃɂ���āv�̊�{�ɗ����A���Ԃa�I�ɉ������悤�Ƃ��Ă������^�[�ɂƂ��āA�����̖��̉��A�\�͂ɂ���ėv���������i�߂���̂́A�F�߂��������Ƃł����B �@�~�����c�@�[�͐_�������슴�Ƃ���Ɋ�Â��M�O�̂��ƂɁA�ގ��g�̐M������v��ڎw���đ����̔_���������Y���ɂ����킢�̒��Ől�����I���܂����B��Ƀ��^�[���u�~�����c�@�[�͐k���Ȃ��玀��ł������B�ނ͐����𐫋}�ɔc�����āA�����ɏ�����Ă��邱�Ƃ��ׂĂ��咣�����B�������A����ŏ\���Ƃ͌����Ȃ��v�ƌ���Ă��܂��B �T�D�~�����c�@�[���l���� �@�~���[���n�E�[���ō��N���肵�Ă����u�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�F���̐��U�ƋƐсv�Ƃ����{�́u�O�����v�͎��̂悤�ȕ��͂Ŏn�܂��Ă��܂��B  �w500�N�ȏ�O�ɃV���g���x���N�i�n���c�j�ŏo�������g�[�}�X�E�~�����c�@�[�ɂ��Ă͔ނƓ�����̐l�ƂƂ��ɁA�㐢�̐l�X����������̉��߂��Ȃ���Ă���B�u�����v�A�u�ْ[�ҁv�A�u���c�̎��v�A�u�M���I�@�����v�ҁv�A�u�@�����v�̊j�v�A�u�����I��q�̕��v�A�u�U�a���ҁv�A�u�d���l�v�A�u���^�[�Ɍ���ꂽ���ԁv�A�u������`�ҁv�A�u�_�̂����ׁv�A�u�_���w���ҁv�A�����Ă���Ɂu�v���Ɓv�ƁA���܂��܂ł���B�x �w500�N�ȏ�O�ɃV���g���x���N�i�n���c�j�ŏo�������g�[�}�X�E�~�����c�@�[�ɂ��Ă͔ނƓ�����̐l�ƂƂ��ɁA�㐢�̐l�X����������̉��߂��Ȃ���Ă���B�u�����v�A�u�ْ[�ҁv�A�u���c�̎��v�A�u�M���I�@�����v�ҁv�A�u�@�����v�̊j�v�A�u�����I��q�̕��v�A�u�U�a���ҁv�A�u�d���l�v�A�u���^�[�Ɍ���ꂽ���ԁv�A�u������`�ҁv�A�u�_�̂����ׁv�A�u�_���w���ҁv�A�����Ă���Ɂu�v���Ɓv�ƁA���܂��܂ł���B�x�@�Ō�ɋ�����ꂽ�u�v���Ɓv�ɂ��ẮADDR�i�h�C�c���勤�a���F�����h�C�c�j�ł̕]���������������Ƃ�������Ă��܂��B�_����J���ҊK����g�D�����Đ������͂ɐ킢�~�����c�@�[�̎p�Ɂu�v���Ɓv�����o�����Ƃ͂���܂łɂ��������悤�ł��B�J�[���E�}���N�X�Ƌ��������t���[�h���b�q�E�G���Q���X�i1820-1895�j�����̂悤�Ȍ����������Ă����Ƃ����܂��B�������A���Ƃ���݂ōĕ]�����Ȃ��ꂽ�̂�1945�N����̓��h�C�c����ł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�`���ɏЉ���~���[���n�E�[���̃~�����c�@�[�E�V���[���i�w�Z�j�⓺���̂ق��Ɋe�n�œ���������A�ʂ�̖��O���Ђ̖��O�A�؎�̐}����A�܃}���N�����̏ё���Ȃǂő傢�Ɍ�������Ă����Ƃ������Ƃł��B���h�C�c���O��1989�N�ɂ̓~�����c�@�[���a500�N�Ղ�����ɍs��Ă��܂��B �@������̎ʐ^�̓~���[���n�E�[���̎s�ǂ̊O�ɗ��~�����c�@�[�̑��ł� �@�����h�C�c�ł������h�C�c�̒n��ł̓~�����c�@�[�̖��O�͂قƂ�Ǖ�����Ȃ������悤�ł��B�h�C�c���牓�����ꂽ���{�ŁA���������~�����c�@�[��m��@��͂���܂���ł����B �@�����̃h�C�c��2001�N�ɐݗ����ꂽ�g�[�}�X�E�~�����c�@�[����iЭ��ʳ��ݔ����ٓ��j���Ɛт̍Ċm�F���n�߂Ă���A���������ۂ̎p��`���o���ēK�ȕ]��������邱�ƂƎv���܂��B �@���^�[���ނ̐M�O�Ɋ�Â��čs�����_���푈�����̂��߂ɍs��������ւ̌Ăт����́A���ʓI�ɑ����̔_���̖���D�����ƂƂȂ�A���̂��Ƃ̓��^�[���g�̐��U�ɂ���������ƂȂ�܂����B������ߐM���ĖI�N�̐擪�ɗ����ē˂��i�~�����c�@�[�ɂ����Ȃ��Ȃ��Ƃ͌����܂���B �@�l�͎����̐M���铹����ނ����Ȃ��̂ŁA���̐l�Ԃ����ꂱ��_�]���邱�Ƃ͍���ł����A��������ɓ����͓��l�̖ڕW���������ł��낤���^�[�ƃ~�����c�@�[�̐l���̎p���傫���Ⴄ���Ƃɋ����܂��B�u��l�̈Ⴂ�v�ɂ��Ă̌��i�K�ł̈�ۂ����t�ɂ���A�u�^���ɐ�����ǂޒ��Ől�Ԃ̎コ��傫����ݍ��ރL���X�g�̈��i�_�̉����j���K�͂Ƃ��ĎƂ߁A�@�����E��ΏۂƂ��ĉ��v��i�߂����^�[�v�Ɓu�����Ɨ��@���܂ރL���X�g���̋��`��_�鐫�ƂƂ��ɎƂ߂Đ_�̗v�������Ȃ̎g���ƔF�����A�����̋�ʂȂ��������͂Ƃ̐킢�ɓ˂��i�~�����c�@�[�v�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B �@�k�Q�Ɛ}���l�@���s�� �@1) Martin Luther (1483-1546)�@Moench-Prediger-Reformator (Verlag Scgnell &Steiner) �@2) Thomas Muentzer�@Ein Aussenseiter der Reformation (Muehlhaeuser Museen) �@3) Luther�@Weisheiten und Lebensstationen : Heinz Stade (Rhino Verlag) �@4) Thomas Muentzer�@Stationen seines Lebens und Wirkens : Heinz Stade (Rhino Verlag) �@5) Auf den Spuren von Martin Luther in Leipzig : Wolfgang Hocquel (Passage-Verlag) �@6) �u�}���e�B���E���^�[�@�@���Ƃɐ��������v�ҁv ���P�`�a �i��g�V���j �@7) �u�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�@�_���`�ҁE�َ��^�I�I���a���ҁE�v���Ɓv H.-J.�Q���c �@ �c���^���E���䏁�� �i�����فj�@�@
�@8) �u���^�[�AЭ�§��A��ټ���� ���̐��U�Ɛ_�w�v�z�̔�r�v �q���� �i�����Ɂj�@9) �u�@�����v�O�啶���@�t�u��܉ӏ��̒��v�v �[��q�N�� �i�u�k�Њw�p���Ɂj ���Ƃ��� 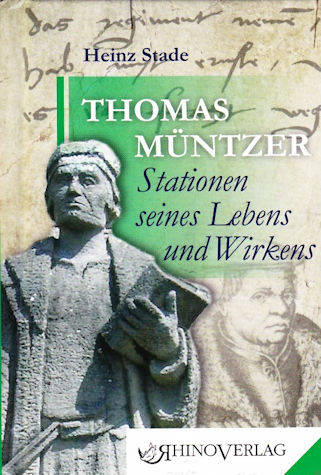 �@���N�A�~���[���n�E�[���œ��肵���u�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�v�̓`�L�i�E�̎ʐ^�j�����^�[�̂���Ɣ�r���Ȃ���ǂݐi�݂܂����B���̌���肵���~�����c�@�[��^�[�Ɋւ���{�A�ȑO����ǂ�ł������^�[�̓`�L�A����܂ł̃h�C�c���s�œ��肵���p���t���b�g�i��Ƀ��^�[�Ɋւ�����́j�Ȃǂ��S�̕����܂܂Ɏ�Ɏ���Ē��߂܂����B �@���N�A�~���[���n�E�[���œ��肵���u�g�[�}�X�E�~�����c�@�[�v�̓`�L�i�E�̎ʐ^�j�����^�[�̂���Ɣ�r���Ȃ���ǂݐi�݂܂����B���̌���肵���~�����c�@�[��^�[�Ɋւ���{�A�ȑO����ǂ�ł������^�[�̓`�L�A����܂ł̃h�C�c���s�œ��肵���p���t���b�g�i��Ƀ��^�[�Ɋւ�����́j�Ȃǂ��S�̕����܂܂Ɏ�Ɏ���Ē��߂܂����B�@���t�̕ǂ͓K�Șa���a�����Q�Ƃ��邱�Ƃł�����x���z���邱�Ƃ��ł��܂����A�L���X�g���̐_�w�A���`�Ɋւ���p��̉��߂ɑ傫�ȕǂ�����̂������Ă���܂��B���{��{�̒��҂�a��҂̓L���X�g���ɐ��ʂ������X�Ȃ̂ŁA�L�x�Ȓ~�ςɊ�Â��������Ȃ���Ă��܂��B����Ɏ��Ԃ������Ė��킢�����Ǝv���Ă��܂��B �@�Ƃ肠�����A���i�K�ł̗����͖{���ɏq�ׂ��͈͂ɂƂǂ܂��Ă��܂����A�Z����{�ɋA�����Ă������A���̃e�[�}�ɖv�����Ă������X�͂ƂĂ������[�����̂ł����B���̗���Ђ낢�͂��ꂩ������������ł��B��肠�����A���i�K�ɂ����鎩���̂��߂̔��Y�Ƃ��Ă����܂��B �����R�O�N�W��21���@��ыL |