稲林昌二
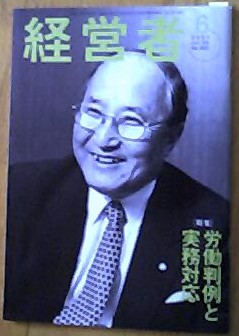 『イメージが先行するとか、イメージ倒れになるとか、さらにはイメージ選挙などというように、イメージという言葉はどこか本質とは乖離した虚像というニュアンスで用いられる場合がある。だが、私たちが日常の生活や仕事の中で行なっている思考やコミュニケーションの主役は案外、イメージであるのかもしれない。
『イメージが先行するとか、イメージ倒れになるとか、さらにはイメージ選挙などというように、イメージという言葉はどこか本質とは乖離した虚像というニュアンスで用いられる場合がある。だが、私たちが日常の生活や仕事の中で行なっている思考やコミュニケーションの主役は案外、イメージであるのかもしれない。
誤解を恐れずにいえばイメージこそが人間の心を動かし、集団をまとめ上げ、共通の目的に向かって動かす情報の根源であるということができそうだ。つまり、人はさまざまな情報を言葉にならない、記号化できない、もちろん数値化も困難な心の底に取り込まれるイメージ(心象)として受け止め、それを凝視する中で浮かんできたイメージのある部分を言葉や論理に置換えて他者に伝えたり、自分で書き留めたりしている。
思考や他とのコミュニケーションが皮相的、記号的に流れるのを避けて、物事の本質に近づくために、あるいは他者により正しく自己を伝えるために私たちは言語や記号、数値データの背景にあるイメージをまともに見据えていく必要がありそうだ。人が物事を決める時に行なう情報処理の大きな部分が、心の中に浮かびくるイメージの吟味、新しいイメージの形成であるとすれば、自らを振り返る時も他者を思いやる時も言葉にならない深層にどこまで想いをいたせるかが大切だと思う。
具体的な方法としては、ナレッジマネジメントでいわれる「暗黙知」の取り扱いにもヒントがありそうだ。ここには醗酵、醸成、熟成などという、お酒飲みが喜びそうなキーワードも並んでいる。
イメージに働きかけるコミュニケーションは人や組織がいまよりもっと知的に洞察的になることを求めている。デジタル全盛の今日だが、人間の智に対するアプローチにはアナログ思考が不可欠なのだ。コンピュータを用いたシステムがイメージを深耕する助けになれるかどうかも今後の課題である。イメージを効果的に取り扱える「反応槽」のようなシステムができるとよいのではないかと思っている。』
「後日の言い訳」
この原稿はある友人からの依頼で今年の連休前に投稿させられたものです。日経連の機関誌「経営者」というのは大抵の会社には送られてくるものだそうで、この話を引受けた後で総務部長に尋ねると「うちの会社にも毎月きてますよ」とのこと。あわてたが後の祭り、原稿掲載誌が届いたときは特別に付箋をつけて回覧などしないことをくれぐれもよろしくと頼んだ。
誌面は1ページに二人の投稿を組み合わせて「交差点」という趣向、なんだかバトルのようでこれも頭痛のたね。最後ははらを決めて日頃思っていることを書くことにした。年来のテーマ「イメージリアクタ」が下敷きにあることは私を知る人にはお分りいただけると思う。提出原稿はプロの編集者によって文体が整えられ、タイトルも編集者が付け直してくれた。
掲載誌発行後、編集部から謝礼として京都は「一保堂」の銘茶が送られてきた。久しぶりに家人の喜ぶ顔をみた。
平成13年6月10日 稲林記
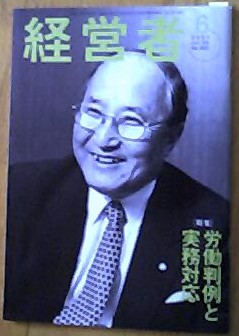 『イメージが先行するとか、イメージ倒れになるとか、さらにはイメージ選挙などというように、イメージという言葉はどこか本質とは乖離した虚像というニュアンスで用いられる場合がある。だが、私たちが日常の生活や仕事の中で行なっている思考やコミュニケーションの主役は案外、イメージであるのかもしれない。
『イメージが先行するとか、イメージ倒れになるとか、さらにはイメージ選挙などというように、イメージという言葉はどこか本質とは乖離した虚像というニュアンスで用いられる場合がある。だが、私たちが日常の生活や仕事の中で行なっている思考やコミュニケーションの主役は案外、イメージであるのかもしれない。