あちこち歩き:
はじめに
昨年の秋に夫婦でスイスを巡ってきたことは別のところでお話をさせていただきました。 美しい自然に囲まれた町や村を楽しんできた中で、帰国後、改めて味わうことになったのが、シラー作の「ヴィルヘルム・テル」です。はじめにお断りしておきますがスイスの中でも大きな部分を占めるドイツ語圏では私たちの耳になじんでいる「ウィリアム・テル」(英語)ではなく、ドイツ語表記の「ヴィルヘルム・テル」(Wilhelm Tell)が正しい表記であり、ドイツのワイマールで執筆されたシラーの戯曲もタイトルは「ヴィルヘルム・テル」です。  ルツェルンから出港した船を追いかけてくるカモメ 1.フリューエレンへの船旅 スイスの観光都市ルツェルンの駅前に広がる大きな湖、通称ルツェルン湖と呼ばれるフィアヴァルトシュテッテ湖はモミジの葉っぱのような形をしています。その西北端に位置するルツェルンからみて一番奥の東南端はフリューエレンの町です。スイスの旅行パスは主要な湖の船に適用されるので、船の上からゆっくりと景色を眺めたい私たちには好都合です。ルツェルンからフリューエレンへ3時間近い船旅を楽しむことができました。  フリューエレンを目指して船は進みます 途中の町や村の乗船場に立ち寄りながら穏やかに進む船の上で、食事や飲み物をいただき、付近の景色を写真に撮りました。後で眺めてみると、その中に貴重な風景があったのです。
2.ウィリアム・テルの村  ウィリアム・テル親子像 フリューエレンの港からバスで10分ほどのアルトドルフという村に着きました。テル・デンクマルというバス停で降りるとすぐそばの小さな広場に塔が立っています。それがウィリアム・テル親子の像を配した記念塔です。ウィリアム・テルが息子の頭の上に置かれた林檎を射た伝説の場所がここアルトドルフの広場であったと言われています。付近にはウィリアム・テルの芝居が上演されるテル劇場があり、観光案内所を兼ねています。テル親子の記念塔から右方向に緩やかな坂を上り始めたところに本屋さんがあったので、シラーの「ヴィルヘルム・テル」(レクラム文庫)を入手しました。ここへ来ることを決めた時から、所縁の場所でドイツ語の原著を買うのを楽しみにしていました。アルトドルフを1時間ほど歩いてから、「テルバス」という直行バスで車窓に湖を見ながらルツェルンへ戻りました。   ウィリアムテル劇場 と テル記念塔全景 3.シラーの「ヴィルヘルム・テル」 シラーの「ヴィルヘルム・テル」は全五幕十五場の大作です。各幕ごとのタイトル(筆者の解釈)は次のようになります。 ① 第一幕 「発端」 ② 第二幕 「三州の団結」 ③ 第三幕 「林檎の的」 ④ 第四幕 「代官射殺と民衆の蜂起」 ⑤ 第五幕 「大団円」 よく知られた「林檎の的」の場面(第三幕)を中心に、代官の圧制に苦しむ民衆(第一幕)が、スイス(当初は三州)独立のために立ち上がる過程(第二幕)、林檎を見事に射抜いた後で逮捕連行されるテルが嵐の湖を進む船から逃れて、代官を待ち伏せ射殺すのと呼応して民衆が蜂起し(第四幕)、勝利を収める(第五幕)までが描かれています。 第一幕でウーリー州の湖畔から始まる物語は湖の東岸にあるシュヴィーツ州、南西部に広がるウンターヴァルテン州での事件を織り込みながら展開します。第二幕では湖の西岸にあるリュートリーでひそかに行われる三州の盟約があり、第三幕の林檎の的は前述のアルトドルフの広場です。第四幕はフィアヴァルトシュテッテ湖の東岸からシュヴィーツ州の山中が舞台となり、第五幕はウーリー州のビュルグレンにあるテルの家で大団円を迎えます。 戯曲は上記三州の民衆の動きを軸に、テルの活躍、関係する人々のエピソードが織り込まれており、大きな広がりを持って描かれています。 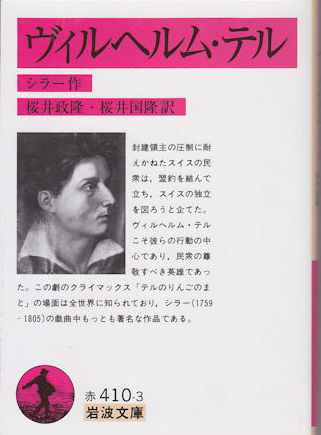 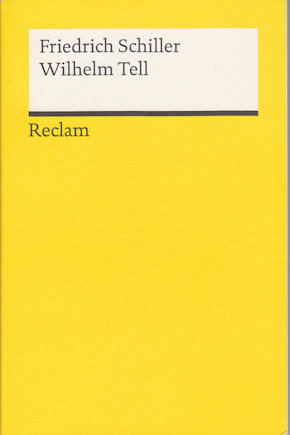 岩波文庫の「ヴィルヘルム・テル」 と レクラム文庫のWilhelm Tell シラーは1804年に、スイスに伝わる伝承をもとに「ヴィルヘルム・テル」を書き上げましたが、その翌年に45歳で没したため、これが遺作となりました。 ひとつ残念なことは19世紀半ばになって、歴史学者たちの研究でテルが実在の人物ではないことが明らかになってしまいます。けれども、スイスの人々はスイス建国の象徴としてテルの伝承を大切にしており、シラーの戯曲によって世界的に知られるようになったことを喜んでいるようです。生涯スイスを訪れることがなかったシラーの記念碑が湖の東岸に建てられているのです。 4.ロッシーニの歌劇「グリエルモ・テル」 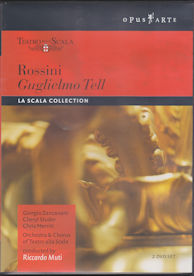 小学校の音楽の時間に聴いた「ウィリアム・テル序曲」は終盤のスイス軍の行進がいまも耳に残っています。ロッシーニがイタリア語の台本で作曲した「ウィリアム・テル」のイタリア語のタイトルは「グリエルモ・テル」と表記されています。今回、DVDを入手して鑑賞してみると、全四幕で合計4時間のこれも大作です。ロッシーニの使用した台本はフランス語版がもとになっていると聞きました。フランス語読みの「ギョーム・テル」から転じた「グリエルモ・テル」という名前はちょっとややこしいのですが、物語はシラーの戯曲に沿っていることが分かりました。 小学校の音楽の時間に聴いた「ウィリアム・テル序曲」は終盤のスイス軍の行進がいまも耳に残っています。ロッシーニがイタリア語の台本で作曲した「ウィリアム・テル」のイタリア語のタイトルは「グリエルモ・テル」と表記されています。今回、DVDを入手して鑑賞してみると、全四幕で合計4時間のこれも大作です。ロッシーニの使用した台本はフランス語版がもとになっていると聞きました。フランス語読みの「ギョーム・テル」から転じた「グリエルモ・テル」という名前はちょっとややこしいのですが、物語はシラーの戯曲に沿っていることが分かりました。オペラの「ウィリアム・テル」は歌あり、バレー・ダンスありの多彩な表現で印象強く描かれています。眼目の、テルが息子の頭の上に置かれた林檎を射抜く場面を注意深く見ましたが、一瞬の早業で目に留まる前に林檎は落ちていました。当然のことながら、オペラの冒頭に演奏されるおなじみの「序曲」も改めて鑑賞することができました。 ロッシーニの歌劇「グリエルモ・テル」
5.スイスの独立と神聖ローマ帝国 シラーの戯曲「ヴィルヘルム・テル」を、岩波文庫の日本語訳を中心に読んでみました。ただし、日本語訳も最初の出版が昭和4年なので、ところどころに難しい訳語が出てきます。その時はレクラム文庫のドイツ語表記を参照し、辞書の助けを借りて確認していました。 その中で、しばしば戸惑ったのはスイスの民衆が自由を求めた対象となる支配権力者の実像です。直接的には「代官」が圧制を行っているのですが、その代官を派遣しているのが、「王」であったり「皇帝」であったり、単に「領主」と表記されていたりします。独立を勝ち取った相手はオーストリアであろうと単純に想像していたのですが、この時代、すなわち1300年代の初めにはハプスブルグ家のオーストリアはまだ確立されておらず、スイスの北東部から徐々に勢力を拡張している時であったようです。最高の支配者は神聖ローマ帝国であり、スイスの独立も神聖ローマ帝国から認められたということになります。ところで、その神聖ローマ帝国が分かりにくいのです。学生時代に西洋史をさぼったことが悔やまれます。 ゲーテが「ファウスト」の第一部を書き上げたのは19世紀の初めですが、その時点でも神聖ローマ帝国は存続していて、酔っぱらった学生に「神聖ローマ帝国が余命保つぞ摩訶不思議!」と歌わせています。神聖ローマ帝国の末期はほぼハプスブルグ家によって保たれていましたが、緩やかな支配の中で、現在のドイツを中心として地域は有力な領主や教会、自由都市による割拠状態にあったようです。「神聖ローマ帝国は、神聖でもなく、ローマでもなく、帝国でもない」という揶揄(やゆ)も見られます。 西欧の中でのドイツ、その基盤となった神聖ローマ帝国の支配の歴史について改めて興味を感じています。 6.シラーについて  数年前に初めてドイツのワイマールを訪ねた時、ゲーテハウスを見て、国民劇場前のゲーテとシラーの二人立ちの像(写真:ゲーテ(左)とシラー(右))を確認してから、市庁舎広場に戻る途中、偶然にシラーの住居前を通りかかって中に入りました。シラーが亡くなるまでの数年を過ごした家です。シラーについては詩人として名前を知っている程度だったので、ぼんやりと館内の展示を眺めている中で、彼が愛用した机の上に置かれている戯曲「ヴィルヘルム・テル」の遺稿に目が留まりました。 数年前に初めてドイツのワイマールを訪ねた時、ゲーテハウスを見て、国民劇場前のゲーテとシラーの二人立ちの像(写真:ゲーテ(左)とシラー(右))を確認してから、市庁舎広場に戻る途中、偶然にシラーの住居前を通りかかって中に入りました。シラーが亡くなるまでの数年を過ごした家です。シラーについては詩人として名前を知っている程度だったので、ぼんやりと館内の展示を眺めている中で、彼が愛用した机の上に置かれている戯曲「ヴィルヘルム・テル」の遺稿に目が留まりました。昨年、スイスへの旅を計画する中で、アルトドルフに遠足することを決めた時に、シラーの戯曲(岩波文庫)を購入しましたが、じっくり読んでみたのは前述のReclam文庫版を買って帰った後でした。 シラーという作家に対する本格的な興味もそこから始まりました。ゲーテの作品は以前から読んでいました。ゲーテの伝記には彼がシラーを高く評価して、その早すぎる死を悲しんだことが書かれています。ベートーヴェンの第九で歌われる「歓喜の歌」にはシラーの雰囲気がよく出ているように思います。 7.ウィリアム・テルの風景 シラーの戯曲「ヴィルヘルム・テル」の中で特に重要な場面は、シュヴィーツ州、ウーリー州、ウンターヴァルデン州の三つの州の民衆を代表する人々が代官や領主の圧制に向かって立ち上がるところだと思います。そこで成立した三州の盟約にテルは直接の関与をしていません。腕のよい猟師として、男気のある頼もしい人間として存在が知れ渡っていたテルに対して、三州団結の主導者、シュタイファッハーが「団結すれば弱い者も強くなるものだ」と言ってテルの参加を促したのに対して、シラーはテルに「強い者はひとりでいる時が一番強い」と言わせています。 テルは三州の団結(リュートリーの誓い)には参加していませんが、結果的に民衆の側に立ち、圧制者の代官ゲスラーを討取ることで独立の象徴となりました。このあたりのテルの人間像はあくまでも純朴な、面倒見のよい、正義感の強い男として描かれています。  リュートリーの船着き場 真夜中に三州の代表者が草原にひそかに集まって団結を誓った場所がリュートリーです。リュートリーの名はスイスから帰って、シラーの戯曲を読んで知ったのですが、フィアヴァルトシュテッテ湖を進む船の上から何気なしに撮った写真の中に「リュートリー」の船着き場を見つけて驚きました。上はその写真です。 あとがき これと言った目的を持たない気ままな旅の中で出会った景色や伝承が、帰ってからの楽しみを与えてくれるのは有難いことです。昨年のスイスではウィリアム・テルに出会い、スイス独立の歴史を垣間見て、シラーの戯曲を味わい、神聖ローマ帝国にまで思いを馳せることが出来ました。それらが、これまでの旅の記憶とも結びついて広がって行くのは不思議な気がします。そんな旅をこれからも続けられたら仕合せだと思います。 平成30年3月10日 稲林記
|