あちこち歩き:
え〜、突然ですが私は浄瑠璃が大好きです。最近は出張にポータブルのHDプレーヤを持参するのですが、中味はバッハと義太夫が半々です。いつも聴いている浄瑠璃の中でも好きな曲のひとつが「葛の葉の子別れ」、これは「芦屋道満大内鑑」(あしやどうまんおおうちかがみ)という大曲の中の一段なのですが、文楽でも歌舞伎でもしばしば単独で上演されます。最近「陰陽師」で人気の出ている阿倍清明(安倍清明とも記す)の出生にまつわる「葛の葉姫」の伝説が題材になっているこの曲を聴いているうちに、所縁の土地を訪ねてみたくなりました。
恋しくば尋ねきてみよ和泉なる信太の森のうらみ葛の葉
訪ねる先はこの歌にある大阪の南、堺に近い和泉の地です。
 前日の宿泊地「有馬温泉」は兵庫県の神戸から六甲山の裏側でした。朝食もそこそこに有馬温泉発の直通バスで大阪駅へ出ると、JR電車で阪和線の「北信太」へ向かいます。近畿地方では私鉄が優勢ですが、こちらの方面はJRが良さそうです。大阪駅からJR紀州路快速で鳳(おおとり)にて普通電車に乗り換えて2駅目が目差す北信太でした。大阪から約45分。北信太駅の前には上の写真の「イラストマップ」があります。このあたりでは「きつね」が大スターであることがこのマップのイラストからも伺えます。  葛の葉稲荷へは、駅前の道を鉄道に沿って数分歩いた右手の踏切を渡ったところ、左手へ路地を入ったところで写真の鳥居が目に入ってきます。門前には神社の狛犬に変わって一対のきつねが控えています。このお狐さんはお寺の仁王さんと同じように阿吽(あうん)の二体をはっきりと見て取ることが出来ます。ご存知だと思いますが。「阿」は息をふっと吐いた瞬間、「吽」は息を吸い込んだ瞬間の姿を表しています。二体のきつねはそれぞれ口に何かくわえています。これはやはり間近く寄って見てみたいところ、右側の「阿」像は玉を、左側の「吽」像は巻物を口にくわえています。写真をクリックすると口のところを拡大してご覧いただけます。 葛の葉稲荷へは、駅前の道を鉄道に沿って数分歩いた右手の踏切を渡ったところ、左手へ路地を入ったところで写真の鳥居が目に入ってきます。門前には神社の狛犬に変わって一対のきつねが控えています。このお狐さんはお寺の仁王さんと同じように阿吽(あうん)の二体をはっきりと見て取ることが出来ます。ご存知だと思いますが。「阿」は息をふっと吐いた瞬間、「吽」は息を吸い込んだ瞬間の姿を表しています。二体のきつねはそれぞれ口に何かくわえています。これはやはり間近く寄って見てみたいところ、右側の「阿」像は玉を、左側の「吽」像は巻物を口にくわえています。写真をクリックすると口のところを拡大してご覧いただけます。神社入り口に掲げられた「由緒書き」には神社の由来が次のように記されています。
境内に入るとあちらこちらにいろいろな碑が立っていて、このお稲荷さんがただのお稲荷さんではないことがわかります。まずは近いところで芭蕉の句碑、「葛の葉のおもて見せけり今朝の霜」。続いてぐっと遡って平安の和泉式部は「秋風のすこし吹くとも葛の葉のうらみがほにはみえじととぞおもふ」。葛の葉のおもて・うらが問題になっているようですが・・それについてご説明します。葛の葉はふつう3枚が一組ですが、風に吹かれて白い葉裏が見えるところから、「うら(裏)」あるいは「恨み(裏見)」にかかる序詞として「葛の葉」がつかわれていたようです。ところでこの葛の葉神社にある葛の葉は3枚の葉のうち1枚が葉裏を見せている文字通りの「うらみ葛の葉」として神社の紋章にも使われています。   写真は神社の社務所に飾ってあった「うらみ葛の葉」の標本を撮らせていただきました。 裏表(うらおもて)の問題はこのへんにして、もうひとつ葛の葉稲荷には重要な植物があります。それは御神樹になっている二千年を超える大楠で、社殿の南側にそびえています。幹のまわりは11m、高さは21mあり、根元より二つに別れているので夫婦楠とも呼ばれ、いい枝ぶりが四方に繁茂しているので千枝(智恵)の楠とも言い伝えられているそうです。ところでこの大楠に昭和53年に落雷があって大枝が折れてしまったときの不思議なお話がこれも碑に刻まれています。
  要約すると、写真左の大楠の大枝が落雷で折れたその下に白蛇が二体息絶えており、それを見つけた成田さんという方の夢枕に龍神が現れたので右の「二体社」を建立して丁重におまつりしたということです。白蛇二体は長い間樹上から人びとを守ってくれていたものと考えられます。
 先に社殿の周りをひとまわり眺めてからいよいよ葛の葉稲荷に参詣をいたします。入り口の鳥居をくぐると右の写真のようにうっそうとした楠の森に囲まれた社(やしろ)が目に入ってきます。神社を覆う「楠」と「葛の葉」、語呂が似ていますが、特に気にしなくても良いそうです。これは後ほど社務所の方に確認しましたので、念のため・・ 先に社殿の周りをひとまわり眺めてからいよいよ葛の葉稲荷に参詣をいたします。入り口の鳥居をくぐると右の写真のようにうっそうとした楠の森に囲まれた社(やしろ)が目に入ってきます。神社を覆う「楠」と「葛の葉」、語呂が似ていますが、特に気にしなくても良いそうです。これは後ほど社務所の方に確認しましたので、念のため・・拝殿の脇にはやはりこれがなくてはいけません。「葛の葉の子別れ」の名場面、狐の化身であった葛の葉姫が阿倍の童子(後の清明)を小脇に抱えて、口にくわえた筆で障子に「恋しくば尋ねきてみよ和泉なる信太の森のうらみ葛の葉」と書き上げたところが描かれています。   浄瑠璃のお話を、ここまで来るとどうしても聴いてもらいたくなりますが、その前に俗に「信太妻」と呼ばれる葛の葉伝説をご紹介しましょう。『昔、摂津(大阪)に住む阿倍保名(あべのやすな)が信太大明神に参詣し池のほとりで沐浴しているところへ狩人に追われ傷ついた白狐が逃げてきたのをかくまって逃がしてやったところ、保名は追ってきた狩人たちに責められて深い傷を負ってしまいました。その保名のところへ葛の葉と名乗る若い女がたずね介抱をし、やがて二人は夫婦となりひとりの童子が生まれました。六年経ったある秋の日に葛の葉は庭の美しい菊に心をうばわれ、うっかり狐の本性を童子に見られてしまいます。もはやこれまでと葛の葉は前出の一首を障子に残して信太の森へ帰っていってしまいました』(和泉市信太の森ふるさと館発行のパンフレットから要約)このときの童子のちに阿倍清明となります。左の写真は文楽公演チラシに載った狐・葛の葉の人形です。 浄瑠璃のお話を、ここまで来るとどうしても聴いてもらいたくなりますが、その前に俗に「信太妻」と呼ばれる葛の葉伝説をご紹介しましょう。『昔、摂津(大阪)に住む阿倍保名(あべのやすな)が信太大明神に参詣し池のほとりで沐浴しているところへ狩人に追われ傷ついた白狐が逃げてきたのをかくまって逃がしてやったところ、保名は追ってきた狩人たちに責められて深い傷を負ってしまいました。その保名のところへ葛の葉と名乗る若い女がたずね介抱をし、やがて二人は夫婦となりひとりの童子が生まれました。六年経ったある秋の日に葛の葉は庭の美しい菊に心をうばわれ、うっかり狐の本性を童子に見られてしまいます。もはやこれまでと葛の葉は前出の一首を障子に残して信太の森へ帰っていってしまいました』(和泉市信太の森ふるさと館発行のパンフレットから要約)このときの童子のちに阿倍清明となります。左の写真は文楽公演チラシに載った狐・葛の葉の人形です。 「芦屋道満大内鑑」は享保19年(1734年)に竹田出雲が書いた五段組織の時代物の浄瑠璃です。物語は題名が示すように阿倍清明の父保名と後に陰陽博士となる芦屋道満の二人を軸として宮中(大内)までも舞台とする大曲です。その四段目にあたるのが阿倍清明の出生伝説に因んだ「葛の葉子別れ」とそれに続く物語で、近年は「子別れ」の場面だけが単独で上演される事も多い人気曲です。 『妻は衣服をあらためてしをしをと奥より出で、臥したる童子を抱きあげ、乳房を含め抱きしめていはんとすれどせぐり来る、涙は声に先立ちて暫く咽びいりけるが・・』という地の描写に続くわが子への切々たる語りかけの中に「悪あがきをふっつとやめ、手習ひ学問精出してさすがは父の子ほどもあり、器用者と誉められよ。なにをさせても埒あかぬ道理よ狐の子ぢゃものと、人に笑はれ誹られて、母が名までも呼出すな」という言葉が観客の胸を打ちます。 葛の葉稲荷の境内には葛の葉姫に化けた白狐が自らの姿を写して見たと伝えられる「姿見の井戸」があります。葛の葉が無事にこの森に帰り着いたことから、近頃では「無事帰る」というので交通安全祈願にこの神社を訪れる人も少なくないのだそうです。 さて、始めにお見せした駅前のマップでは「葛の葉神社」のほかにも所縁の場所があります。そちらへ向かってみましょうか。はじめに見た駅の案内図では「聖神社」と「鏡池」が関連の史跡のようです。もういちど地図を眺めて見ます。  まずは「清明との子別れの舞台でもある」と書いてある信太の森の中心「聖神社」をめざして葛の葉稲荷からもう一度踏み切りを渡って歩き始めました。この地図では聖神社の方向へまっすぐ行く道があるのかどうかわかりません。自分の方向感覚をたよりになるべく真っ直ぐ真っ直ぐ歩いていくと小学校の校門にぶつかってしまいました。  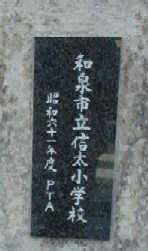 近寄ってみると「和泉市立信太小学校」、阿倍の童子が通った学校?そんなことはないでしょうが、「和泉なる信太の森の小学校」といったところです。聖神社への道はここから難渋を極めます。信太小学校に沿って右に回りこんで裏手に出るとこんどは団地のアパート群に迷い込んでしまいました。通りかかった地元の方に道を尋ねること三度、30分ほど歩いてようやく聖神社にたどり着く事ができました。聖神社は大変に由緒のある神社です。拝殿の奥にある本殿は桃山様式のきらびやかなものでそれが信太の森に囲まれて鎮座しています。   聖神社は延喜式内の旧社で信太大明神とも呼ばれており、現在の本殿は慶長9年(1604年)に豊臣秀頼が片桐旦元を奉行に再建したもので国の重要文化財に指定されてるそうです。 もうひとつの葛の葉伝説所縁の場所「鏡池」は白狐と保名の出会いの場所、童子と子別れの舞台であると伝えられてきました。鏡池は聖神社の神域にあり「手洗池」とも呼ばれているのは神社で神事を行う際に身を清める神聖な池であったとのことです。  聖神社から鏡の池へは社殿の裏を降りていく小道があるのですが、安全のために大回りして団地を通り抜けていきました。池のほとりに和泉市の「信太の森鏡池史跡公園・信太の森ふるさと館」という施設があり、信太の森の「情報と学びのセンター」になっています。館内には信太の森の自然と伝説に関する展示物があり、ボランティアの方が親切に説明をしてくれました。 鏡池から団地を抜けると駅に向かう大通りがあり、ちょうど通りかかったバスに乗るとひと停留所で北信太の駅に戻る事が出来ました。聖神社をめざしたあの山越えの苦労は何だったのかと思いますが、お陰で信太の森を身をもって味わう事が出来ました。帰途は大阪の南の玄関口、天王寺へ出て、もうひとつの所縁の場所である「阿倍清明神社」に向かおうとしましたが、信太の森でスタミナを消耗した足が歩きたがらず、気がついてみたら阿倍野の老舗居酒屋「明治屋」さんのカウンターに座っていました。 あとがき: 「芦屋道満大内鑑」という浄瑠璃が人形芝居で上演されたとき、四段目の後半「信太の森二人奴」の段で、今私たちが文楽で見る「三人遣い」の人形が初めて登場しました。与勘平・弥勘平という二人の大男の動きを強調するために、一人遣いの他の人形に対比させて観客を喜ばせたということです。念願かなって信太の森を・・・「尋ねて来ませ和泉なる、信太の森へと慕ひ行く」とある浄瑠璃の段切れの詞章そのままに歩けたことを喜んでいます。(歩いた日:H17.12.3) 平成18年2月19日 稲林 記
|

