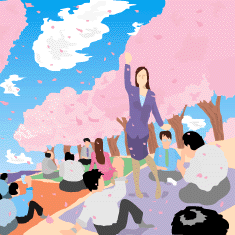 「春は花」などと言っているうちに、今年のお花見シーズンは終わろうとしています。「・・しています」などと未練な言い方をするのは、今日にでも、ふと気が向いて新幹線に飛び乗れば、津軽の弘前城、南部盛岡の石割桜、角館の武家屋敷でお花見が楽しめるのではないかと思うからです。そこのところはJR東日本も心得ていて、「土日フリー切符」だの、「弘前往復割引切符」のようなものを売り出して誘い出しに掛かっています。
「春は花」などと言っているうちに、今年のお花見シーズンは終わろうとしています。「・・しています」などと未練な言い方をするのは、今日にでも、ふと気が向いて新幹線に飛び乗れば、津軽の弘前城、南部盛岡の石割桜、角館の武家屋敷でお花見が楽しめるのではないかと思うからです。そこのところはJR東日本も心得ていて、「土日フリー切符」だの、「弘前往復割引切符」のようなものを売り出して誘い出しに掛かっています。ところで、何故お花見に「反省」が必要かというと、言うまでもありませんが、反省のないところに向上はないからです。それではお花見の「向上」とは何か、なんて、そういうカタイことを言っちゃいけませんが。つまりその、なんですよ。ちょうど今頃、「今年は例年になく良いお花見ができたなあ」と、しみじみ仕合せを噛みしめたい。仕合せを噛みしめられない場合でも、せめてスルメでもいいから噛みしめたい。そういうのが向上ではないでしょうか。こんなことを考え始めたのは、今年のお花見というものがなぜか、上滑りしてしみじみまで行かなかったような気がしているからです。
それじゃあ、去年はどうだったかというと、昨年は史上空前の早咲きで3月中にお花見があらかた済んでしまいました。これはお天気のほうに反省してもらわなければなりません。4月の声を聞かないうちにせかされるようにお花見をしました。日記では3月24日に隅田川東岸の向島へお花見に行っています。「なんで今年はこんなに早くさくらが咲いちまったんだろう?」という素朴な疑問と、「早いとこ出かけないとお花見が出来ずに春が終わってしまう」という危機感、「小学校の入学式に葉桜ということが許されるのだろうか」という義憤、これらがごっちゃ混ぜになっていました。それでも一応、好天気の休日に墨堤を歩き、旧水戸藩下屋敷(通称「梅屋敷」)の庭園から桜餅の長命寺まで足を延ばして、「お花見」の気分を十分に味わうことができました。
 今年恐れていたのは、「また去年のようにバカ早く花が咲いてしまったらどうしょう」という、そのことでした。浦和の西にある会社の前には植えられて10数年の若い桜並木があります。3月の10日を過ぎると毎日、出勤のときに気になり始めました。「ひと雨ごとの暖かさ」などという陽気になってくると、桜より先に敷地内の柳がうっすらと青みをおびてきます。「蕾はまだ固い」と安心しながらも、あと2週間は「がまんしろ、がまんしろ」と語りかけます。なんとか3月28日まで待たせましたが、その日に東京の開花宣言が出ました。
今年恐れていたのは、「また去年のようにバカ早く花が咲いてしまったらどうしょう」という、そのことでした。浦和の西にある会社の前には植えられて10数年の若い桜並木があります。3月の10日を過ぎると毎日、出勤のときに気になり始めました。「ひと雨ごとの暖かさ」などという陽気になってくると、桜より先に敷地内の柳がうっすらと青みをおびてきます。「蕾はまだ固い」と安心しながらも、あと2週間は「がまんしろ、がまんしろ」と語りかけます。なんとか3月28日まで待たせましたが、その日に東京の開花宣言が出ました。都内で会議のあった3月29日の土曜日に今年初めてのお花見をしました。朝、上野駅から本郷へ向かって上野公園、不忍池を横切って歩きながら咲き始めの花を眺ていると、早くもお花見の陣取りが出動しています。人出をあてこんだ出店も準備が始まっているのを横目に不忍通りを横切って、無縁坂から東大の竜岡門脇を通って、春日通の本郷3丁目へと歩き慣れた道を辿りながら、お花見の予感を覚えました。案の定、会議終了後の懇親会がはねると、7〜8名が連れ立って以心伝心で上野へ足が向きます。湯島の天神下から池之端仲町通りのいつもの酒屋さんで飲み物とおつまみを買って、不忍池をまわり、お花見まっさかりのメイン会場、公園中央部を目指しました。「上野公園はお花見の甲子園だ」というのが、いつもの口癖です。
週明けの火曜日、4月1日はさいたま市の政令指定都市がスタートしました。会社のある旧浦和市田島はなんと、さいたま市桜区田島になってしまいました。この時季にまさか「桜区」とは出来すぎです。1日の朝、乗り換えの武蔵浦和で駅の外に出て、ここから別所沼へ続く「さくら並木」を少し歩いて写真を撮ってみました。埼京線の中浦和から武蔵浦和に向かうとき、車窓に見える見事な並木です。地元の人はここでお花見をするのでしょう。ぼんぼりが吊られて、出店もありました。この日はすぐに駅へ引き返したのですが、数日後、会社を訪ねてきた後輩を昼食に誘い武蔵浦和から桜並木を別所沼畔の鰻屋さんまで歩き、念願を達成しました。
 そうこうしているうちに、急な冷え込みの日があるかと思うと、激しい風雨の日がつづき、「あ〜、今年のお花見はもう終わりか」と観念したものです。「30日の日曜日、向島はよかったよ」といって自慢する仲間もいました。出張先の大分でも風雨にあい、タクシーのワイパーをぼんやり眺めていました。ようやく晴れた6日の日曜日に家の周囲を探すと、近くにある会館の桜がまだ見られるというので出かけました。ここは近場でお花見に手ごろな場所なのですが、家のものが「ご近所のひとに見られると恥ずかしい」というので、散歩を兼ねた本当の見るだけの「お花見」をしました。写真だけは沢山撮ってきましたが、あいにくの曇天でいまひとつ浮いた気持ちがしません。このあたりから、「今年はこんなことで終わってしまうのか」とあせりを感じ始めました。
そうこうしているうちに、急な冷え込みの日があるかと思うと、激しい風雨の日がつづき、「あ〜、今年のお花見はもう終わりか」と観念したものです。「30日の日曜日、向島はよかったよ」といって自慢する仲間もいました。出張先の大分でも風雨にあい、タクシーのワイパーをぼんやり眺めていました。ようやく晴れた6日の日曜日に家の周囲を探すと、近くにある会館の桜がまだ見られるというので出かけました。ここは近場でお花見に手ごろな場所なのですが、家のものが「ご近所のひとに見られると恥ずかしい」というので、散歩を兼ねた本当の見るだけの「お花見」をしました。写真だけは沢山撮ってきましたが、あいにくの曇天でいまひとつ浮いた気持ちがしません。このあたりから、「今年はこんなことで終わってしまうのか」とあせりを感じ始めました。翌週に入るとあちこちで盛大な葉桜が見られるようになりましたが、「まだあきらめるの早い」と、気を取り直して週末には家族で秩父を目指します。今回もアプローチは定峰峠です。小川町から東秩父村に向かうと、里は見ごろなお花見日和です。定峰の頂上付近には桜の木が沢山あるのですが、こちらはまだ早いようです。目指すは秩父の羊山公園。ここは地元で有名な桜の名所です。例年東京より1週間から10日遅れて満開になります。ふもとの駐車場に車を停めて、小高い、山というより丘と呼びたいような羊山へ上がる道々振り返ると街全体の姿がよく見えてきます。山上の桜はほぼ満開、絶好のお花見びよりに、ここでも陣取りのひとがちらほら見えますが、子供を遊ばせている人もいてやはりどこか長閑です。これでようやく「お花見」ができたと安心して、お昼を目当てのお蕎麦屋さんへ向かいました。
秩父では札所のお寺がそれぞれに花を競っています。さくらもいろいろな種類のものが見られるはずです。昨年御開帳でにぎわった札所に、春のお遍路さんがやってきます。花に見守られての札所めぐりもよいものでしょう。羊山の桜と上から見た市内の風景を写真に撮りました。

